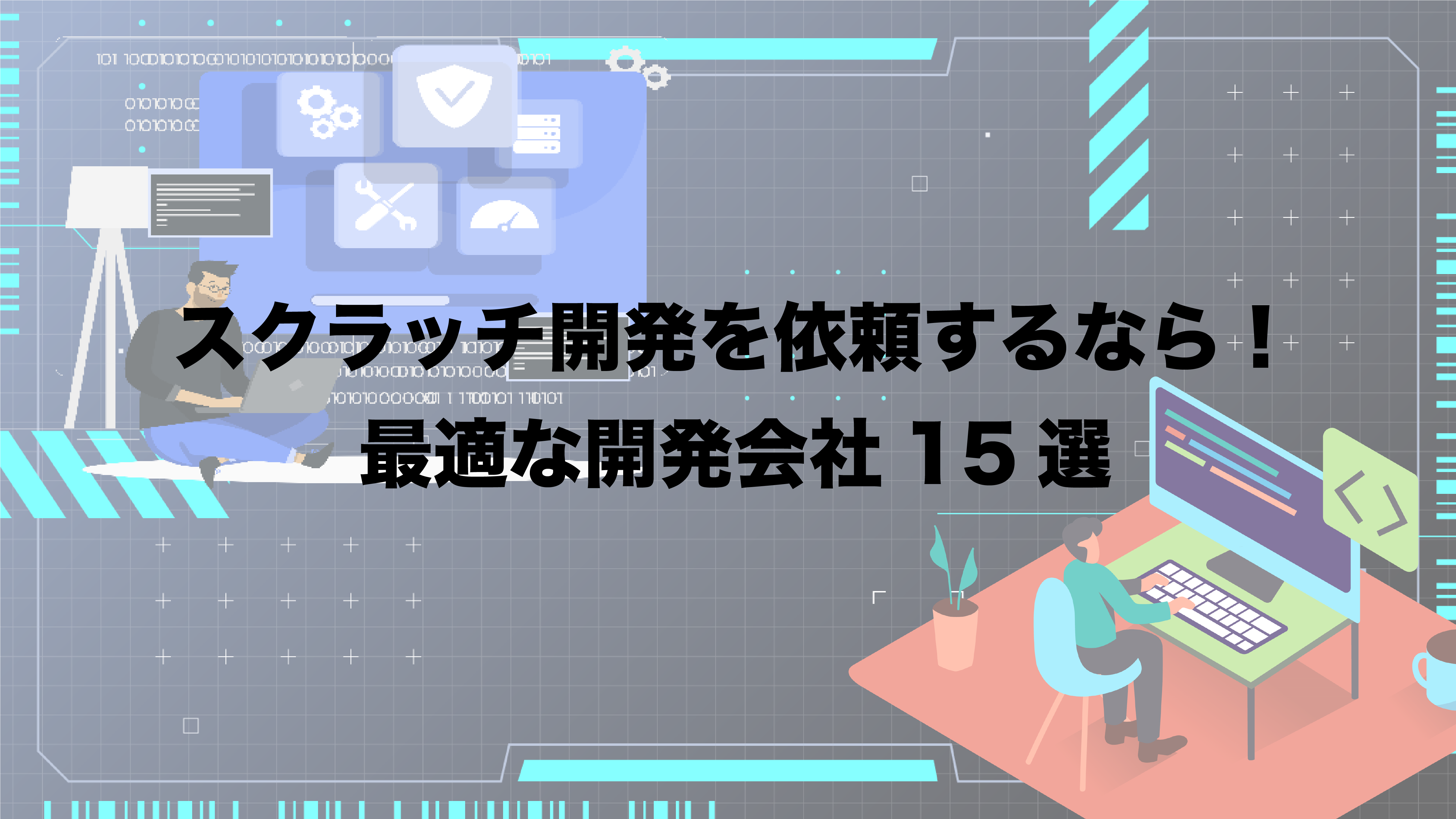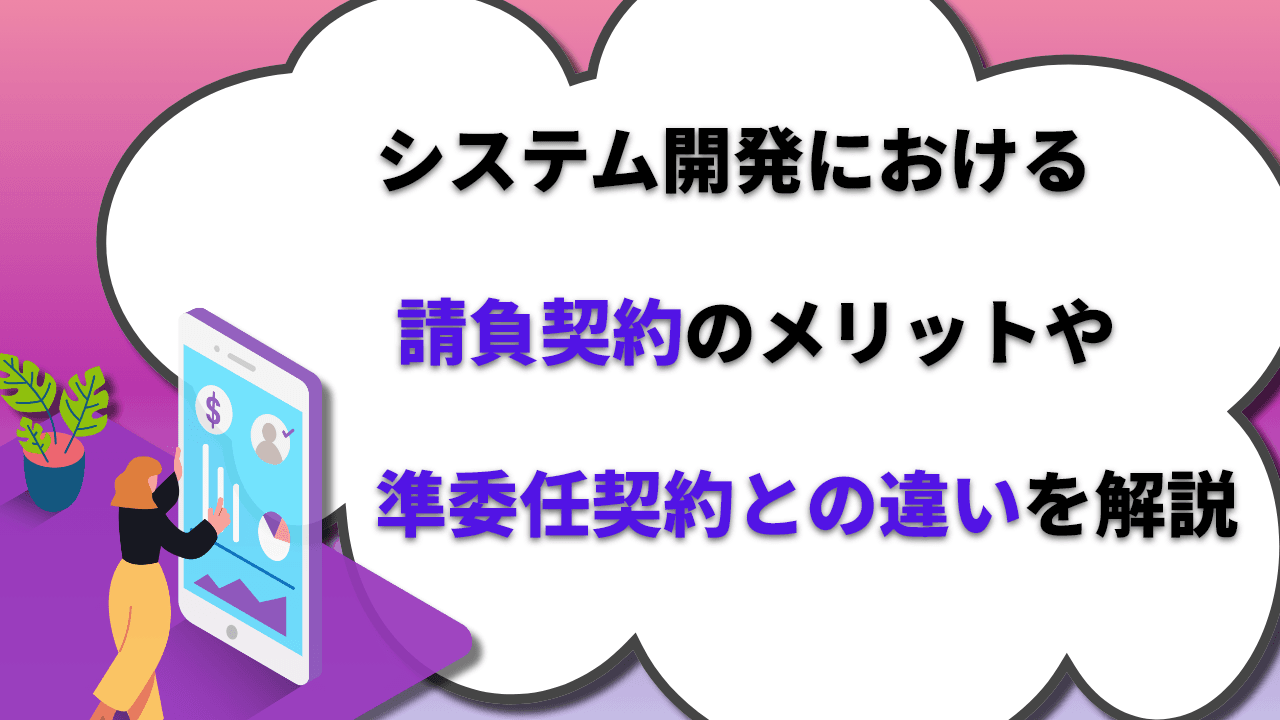スクラッチ開発とは?メリットやパッケージ開発との違いも解説!
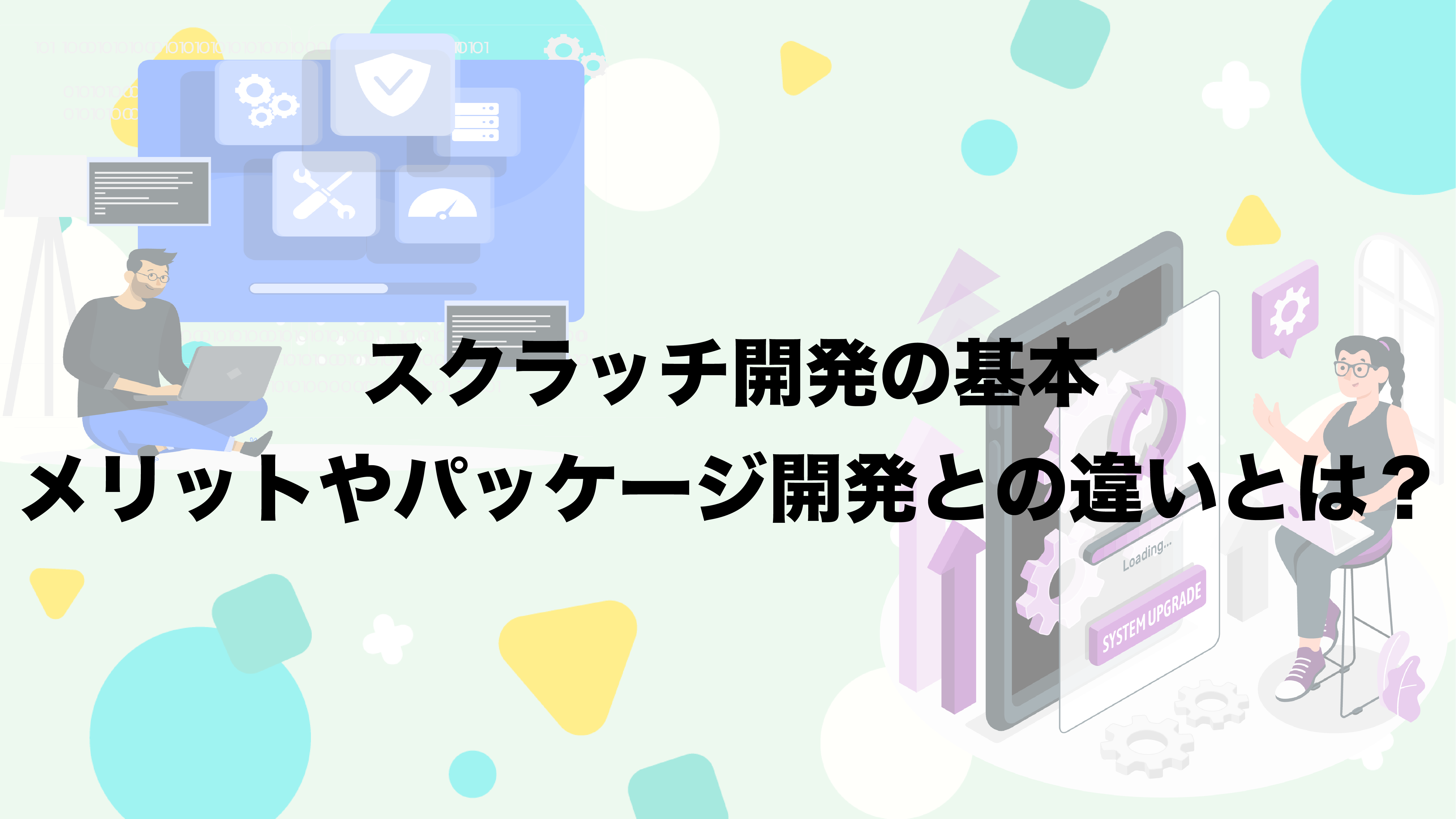
スクラッチ開発は、独自の要件やビジネスニーズに完全に合わせたシステムをゼロから開発する手法です。これにより、企業は特定の要求に応じたカスタマイズされたソリューションを得ることができますが、その一方で開発コストや時間がかかることも特徴です。
本記事では、スクラッチ開発の基本概念から進め方、メリット・デメリット、パッケージ開発との違いについて詳しく解説します。
さらに、スクラッチ開発が向いているプロジェクトと向いていないプロジェクトの特徴についても触れます。最後に、スクラッチ開発を依頼する際に重要な発注先の選び方について具体的なポイントを紹介します。
スクラッチ開発を検討している企業の皆様が、最適な選択をするための参考にしていただける内容となっています。是非、この記事を通じてスクラッチ開発の全体像を理解し、自社に最適なシステム開発の手法を見つけてください。
スクラッチ開発とは?
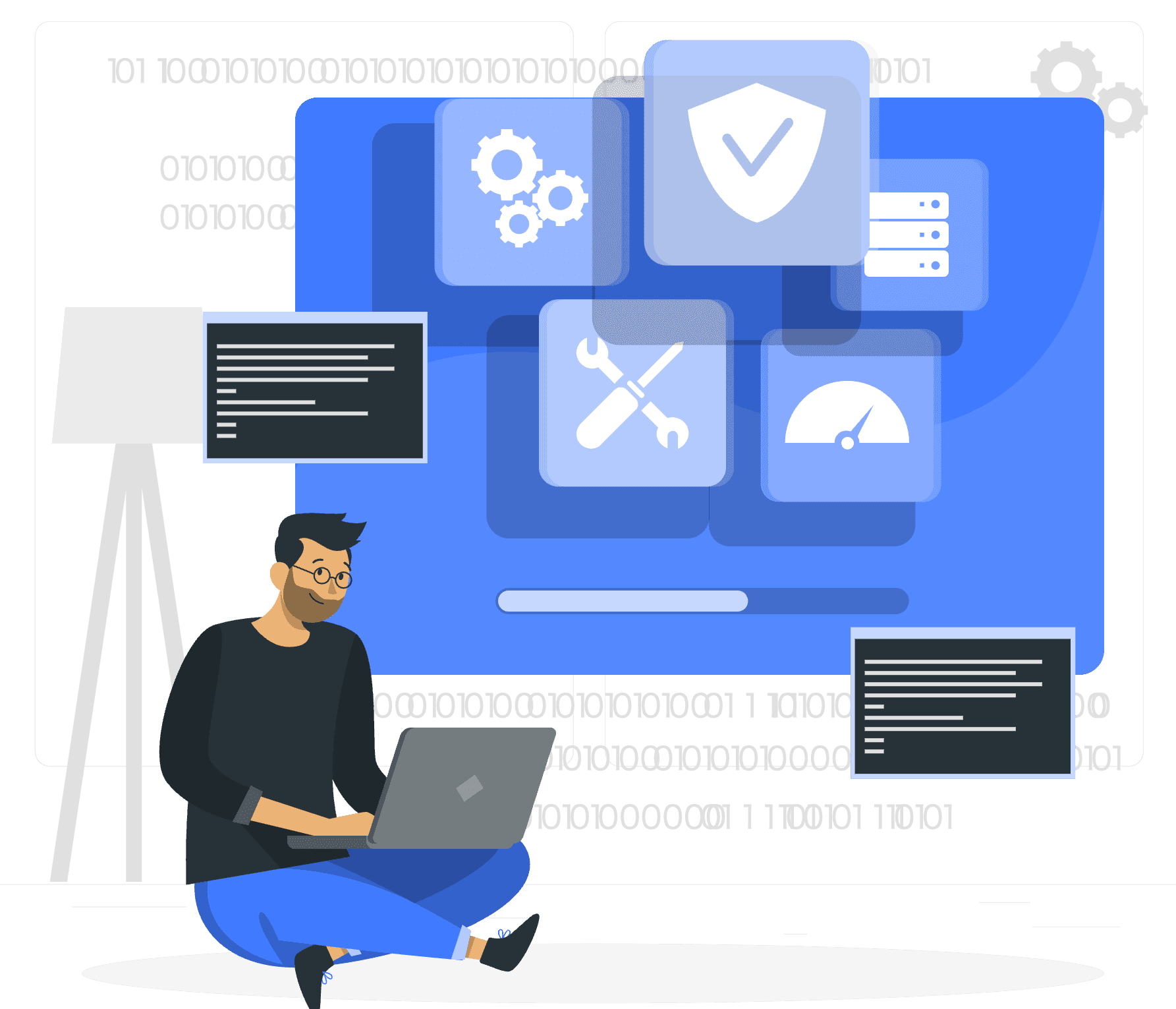
スクラッチ開発は、企業の特定の要件やニーズに合わせてシステムをゼロから構築する手法です。このセクションでは、スクラッチ開発の基本的な概要から、フルスクラッチ開発との違い、パッケージ開発の定義、両者の比較、そしてスクラッチで開発したシステムの著作権について詳しく解説します。
スクラッチ開発の概要
スクラッチ開発は、企業や組織が特定の要件やビジネスニーズに合わせて、既存のソフトウェアやテンプレートを使用せずにゼロからシステムやアプリケーションを構築する手法です。これにより、カスタマイズ性が高く、ユーザーの具体的な要求に完全に応えることができます。スクラッチ開発は、独自の機能や特殊な業務プロセスが必要な場合に最適です。
この開発手法の利点には、システムが完全にビジネスのニーズに合致すること、不要な機能が含まれず、システムのパフォーマンスが最適化されることが挙げられます。また、開発者はシステムの内部構造を完全に理解しているため、後の保守や拡張が容易になります。
一方で、スクラッチ開発にはデメリットもあります。開発コストが高く、開発期間も長くなる傾向があります。さらに、初期段階での要件定義が不十分な場合、プロジェクトが失敗するリスクが高まります。そのため、スクラッチ開発を選択する際には、プロジェクトの規模や要件の複雑さ、予算とスケジュールを慎重に検討する必要があります。

開発オクトパス
スクラッチ開発とフルスクラッチ開発の違い
スクラッチ開発とフルスクラッチ開発は、どちらもシステムやアプリケーションをゼロから構築する手法ですが、いくつかの重要な違いがあります。
スクラッチ開発は、既存のソフトウェアやテンプレートを利用せずに、特定の要件に合わせてシステムを一から開発する手法です。これは、必要な機能を完全にカスタマイズできる柔軟性を提供します。たとえば、既存のフレームワークやライブラリを活用することもありますが、システム全体が特定のニーズに応じて構築されます。
一方、フルスクラッチ開発は、全てのコードと機能を完全に一から開発する手法を指します。ここでは、一般的なフレームワークやライブラリすら使わず、システム全体をゼロから構築します。これにより、システムのすべての部分が特定の仕様に完全に合わせられるため、最もカスタマイズ性が高く、非常に特化したニーズに対応できます。
主な違いは、カスタマイズの深さと使用するリソースです。スクラッチ開発では既存のリソースを適度に活用することで、開発効率を高めることができますが、フルスクラッチ開発はすべてを自前で構築するため、時間とコストが大幅に増加します。
これらの違いを理解することで、プロジェクトの要件に最適な開発手法を選択することができます。
パッケージ開発とは
パッケージ開発とは、一般的なビジネスニーズに対応するために事前に設計されたソフトウェアを使用する手法です。これは、特定の業務プロセスや機能を提供する既製のソフトウェアパッケージを導入することを指します。この手法では、企業は既存のソリューションを導入し、必要に応じてカスタマイズを行うことで短期間でシステムを稼働させることができます。
パッケージ開発の主な利点には、導入の迅速さとコストの低さがあります。既製のソフトウェアはすでに開発とテストが完了しているため、導入にかかる時間と労力が大幅に削減されます。また、パッケージソフトウェアは多くのユーザーに使用されているため、信頼性と安定性が高いことが多いです。
しかし、パッケージ開発には制約もあります。既製のソフトウェアは、全てのビジネスニーズに完全には対応できない場合があり、カスタマイズには限界があります。また、企業の特定の業務プロセスに完全に一致しない場合、運用上の問題が発生する可能性があります。
パッケージ開発は、一般的な機能が必要な場合や迅速な導入が求められる場合に適していますが、特定のカスタム要件が多いプロジェクトには不向きです。
スクラッチ開発とパッケージ開発の比較
| スクラッチ開発 | パッケージ開発 | |
|---|---|---|
| カスタマイズ性 | 完全なカスタマイズが可能。特定の要件や業務プロセスに完全に対応できる。 | 限定されたカスタマイズのみ可能。一般的な業務プロセスに対応。 |
| 導入速度 | 開発期間が長く、導入までに多くのステップが必要。 | 迅速な導入が可能。設定とカスタマイズだけで短期間で運用を開始できる。 |
| コスト | 高い初期投資が必要。開発期間中の費用が継続的に発生。 | 初期導入費用が低い。ライセンス費用やサポート費用が発生することも。 |
| 保守・運用 | 開発者がシステムを完全に理解しているため、保守や拡張が容易。 | ソフトウェアベンダーのサポートを利用でき、定期的なアップデートが提供される。 |
| リスク | プロジェクト失敗のリスクが高い。予期せぬ技術的な問題が発生する可能性。 | ベンダーロックインのリスクがある。将来的な柔軟性が制限される。 |
スクラッチで開発したシステムの著作権とは
スクラッチ開発によって作成されたシステムの著作権は、通常、開発者または開発会社に帰属します。しかし、契約内容によっては、クライアントが著作権を取得することも可能です。以下のポイントを理解しておくことが重要です。
著作権の帰属
デフォルトでは、スクラッチ開発を行った開発会社が著作権を保有します。これは、開発会社がコードを書き、システムを構築したためです。
ただし、契約書で著作権の譲渡が明記されている場合、クライアントが著作権を取得することができます。これには、著作権の譲渡に関する明確な条項が必要です。
契約内容の確認
著作権に関する条項は契約書に明記されている必要があります。以下の点に注意しましょう。
著作権の譲渡条項: クライアントが著作権を取得する場合、この条項が明確に記載されていることを確認します。
使用権とライセンス: 著作権が開発会社に残る場合でも、クライアントがシステムを自由に使用できるよう、使用権やライセンスが付与されることが一般的です。
著作権の範囲
スクラッチ開発では、以下の部分について著作権が発生します。
ソースコード: 開発された全てのコードに対する著作権。
デザイン: UI/UXデザイン、グラフィックスなどのビジュアル要素に対する著作権。
ドキュメント: システムの設計書、仕様書、ユーザーマニュアルなどのドキュメントに対する著作権。
著作権の利点とリスク
利点: クライアントが著作権を持つ場合、システムの改変、再利用、販売などを自由に行うことができます。
リスク: 著作権の取り扱いが不明確な場合、後に法的トラブルが発生する可能性があります。契約書での明確な取り決めが必要です。
著作権の取り扱いを明確にすることで、開発後のトラブルを防ぎ、システムの自由な利用が可能になります。契約内容を十分に確認し、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。

開発オクトパス
スクラッチ開発の進め方
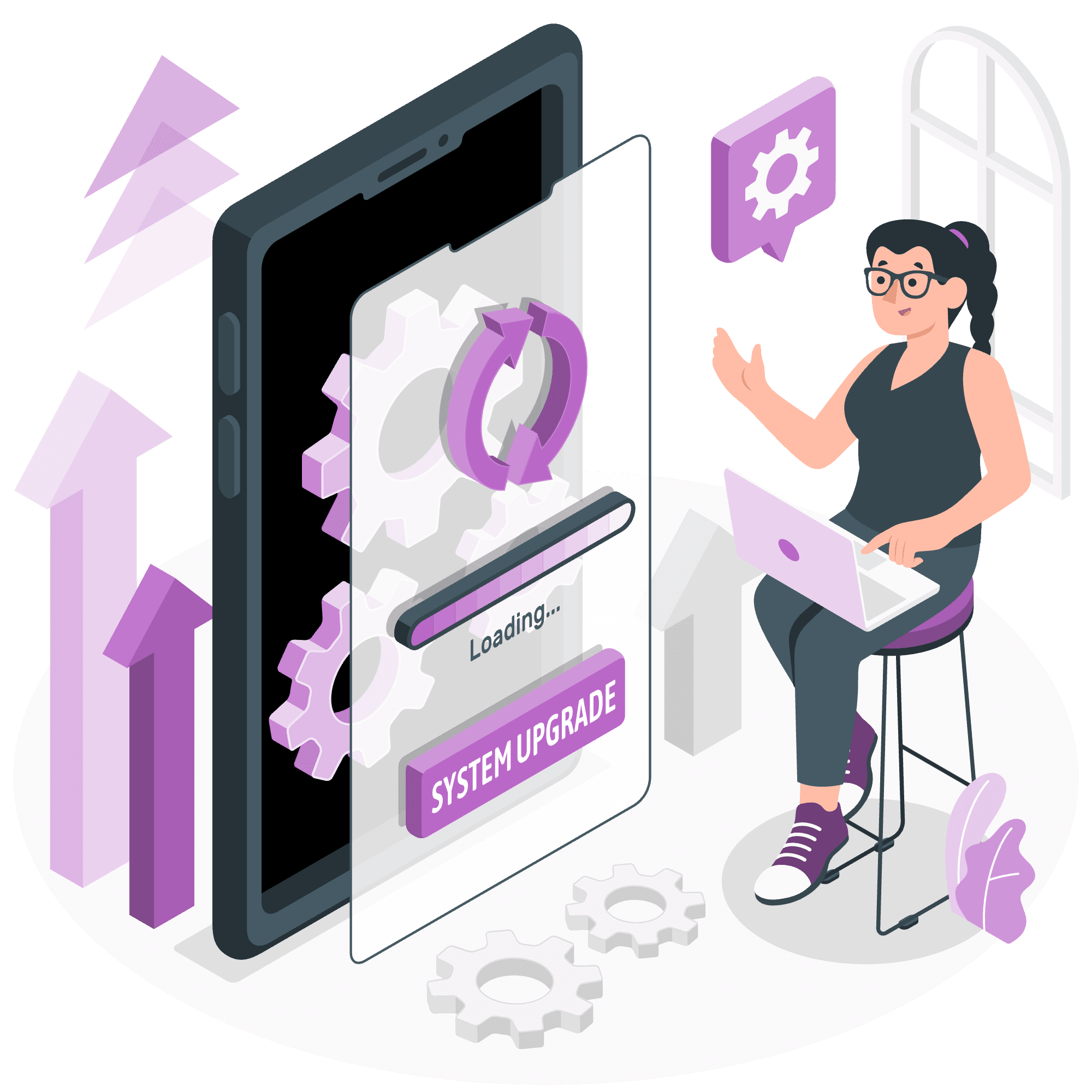
スクラッチ開発は、システムをゼロから構築するプロセスで、以下のステップを踏むことが一般的です。このセクションでは、要件定義から運用までの各フェーズについて詳しく解説します。
要件定義
要件定義は、スクラッチ開発の最初のステップであり、プロジェクトの成功に不可欠です。このフェーズでは、クライアントのビジネスニーズと目標を詳細に把握し、それに基づいてシステムの機能や仕様を明確にします。
要件定義には、クライアントとのミーティング、ワークショップ、インタビューなどを通じて情報を収集し、ユーザーストーリーやユースケースを作成することが含まれます。
これにより、プロジェクトの方向性が定まり、後の設計・開発フェーズに向けた基盤が構築されます。明確な要件定義は、プロジェクトのスコープを管理し、後々の変更要求を最小限に抑えるためにも重要です。
設計
設計は、要件定義に基づいてシステムの具体的な構造を決定するフェーズです。この段階では、システム全体のアーキテクチャを設計し、各コンポーネントの詳細を定めます。
設計には、データベース設計、ユーザーインターフェース設計、システムインフラ設計などが含まれます。これにより、開発チームが一貫性を持って開発を進めるための明確なガイドラインが提供されます。
設計フェーズでは、図やモデルを用いて視覚的にシステムの構造を示し、各部分の関係性やデータフローを明確にすることが重要です。これにより、後の開発フェーズでの効率が向上し、プロジェクトのリスクを低減することができます。
開発
開発フェーズでは、設計に基づいてシステムを実際に構築します。この段階では、プログラミングやコーディングが中心となり、各コンポーネントが実装されます。
開発者は、設計書を参照しながら機能を実装し、各モジュールが正しく連携するようにします。また、バージョン管理システムを使用して、コードの変更履歴を管理し、チーム内での統合をスムーズに進めます。
このフェーズでは、単体テストも並行して行われ、各機能が個別に正しく動作することを確認します。適切なコーディングスタンダードとレビューの実施により、コードの品質を確保し、バグや問題の発生を最小限に抑えることが重要です。
テスト
テストフェーズは、開発されたシステムが設計通りに機能し、要件を満たしていることを確認する重要な段階です。
テストには、単体テスト、結合テスト、システムテスト、ユーザー受け入れテスト(UAT)など、さまざまなレベルがあります。
まず、各コンポーネントが個別に機能するかを確認する単体テストを実施し、その後、各コンポーネントが連携して正しく動作するかを確認する結合テストを行います。システム全体の動作を確認するシステムテストでは、システムの性能や安全性も検証します。
最後に、ユーザーが実際の運用環境でシステムを使用して確認するユーザー受け入れテストを実施し、実際の使用に耐えるかを確認します。このフェーズで発見された不具合や問題は修正され、再度テストが行われることで、システムの品質が保証されます。
リリース
リリースフェーズでは、完成したシステムを本番環境に展開し、実際の運用を開始します。ユーザーに対するトレーニングやサポートも行い、スムーズな移行をサポートします。リリース後も、システムの監視を続け、必要な修正や最適化を行います。
運用
運用フェーズでは、リリースされたシステムが日常業務で安定して稼働するように管理・監視を行います。システムのパフォーマンスを定期的にチェックし、障害や不具合が発生した場合には迅速に対応します。
また、ユーザーからのフィードバックを収集し、必要な改善や機能追加を行うことで、システムの持続的な改善を図ります。運用には、バックアップの定期実行、セキュリティパッチの適用、システムのメンテナンスなども含まれます。これにより、システムが長期間にわたり信頼性とパフォーマンスを維持することができます。
スクラッチ開発のメリット/デメリット

スクラッチ開発には、独自性の高いシステムを構築できるなどのメリットがある一方、コストや時間がかかるなどのデメリットも存在します。このセクションでは、スクラッチ開発のメリットとデメリットについて詳しく解説します。
スクラッチ開発のメリット
独自性の高いシステムを構築できる
スクラッチ開発は、特定のニーズや要件に完全に合わせたシステムをゼロから構築できるため、独自性の高いシステムが実現します。
長期的にシステムを運用できる
企業のニーズに合わせて設計されたシステムは、将来的な変更や拡張に対応しやすく、長期的に運用しやすいです。
費用対効果が高い
初期コストは高いものの、カスタマイズ性の高さと長期的な運用を考慮すると、最終的には費用対効果が高いです。
拡張性の高いシステムの構築が可能
スクラッチ開発では、設計段階から将来的な拡張を見越してシステムを構築できるため、ビジネスの成長に応じて柔軟に対応できます。
スクラッチ開発のデメリット
コストがかかる
スクラッチ開発はゼロからシステムを構築するため、初期投資が高くなります。特に、大規模なプロジェクトではコストが膨大になることがあります。
開発するのに時間がかかる
既製のソフトウェアを利用せず、全てを新たに開発するため、開発期間が長くなります。プロジェクトの完成までに多くの時間が必要です。
開発ベンダーによってシステムのクオリティが異なる
開発会社の技術力や経験により、システムの品質が大きく変わります。適切なベンダー選びが重要であり、失敗すると期待通りの成果が得られないことがあります。
スクラッチ開発に向いている開発/向いていない開発
スクラッチ開発が適しているプロジェクトと適していないプロジェクトの特徴を解説します。このセクションでは、納期や予算、システムの重要度など、スクラッチ開発の向き不向きを明確にします。
スクラッチ開発に向いている開発
納期/予算に余裕がある
スクラッチ開発はゼロから構築するため、時間とコストがかかります。したがって、納期や予算に余裕があるプロジェクトに向いています。
コア業務に関するシステム
企業の中核を成す業務プロセスに特化したシステムは、スクラッチ開発によって最大限のカスタマイズ性と効率を実現できます。
独自性の高いシステム
特定のビジネスモデルやプロセスに固有の機能を持つシステムは、スクラッチ開発で構築することで独自性を維持し、競争優位を確保できます。
機能の追加や改修が頻発する可能性のあるシステム
スクラッチ開発は、将来的な拡張や機能追加を見越して設計されるため、変更が頻繁に発生するシステムに適しています。
スクラッチ開発に向いていない開発
システム開発に予算を割けない開発
スクラッチ開発はコストが高いため、限られた予算では困難です。既成のソリューションの方が費用を抑えられる場合があります。
システム開発に時間をかけられない開発
スクラッチ開発には時間がかかるため、迅速な導入が求められるプロジェクトには不向きです。短期間での稼働が必要な場合は他の手法を検討します。
ノンコア業務に関するシステム
重要度の低い業務プロセスに対しては、既成のパッケージソフトウェアの方が適しています。スクラッチ開発はリソースの無駄になる可能性があります。

開発オクトパス
スクラッチ開発の発注先の選び方
スクラッチ開発の発注先を選ぶ際には、実績の確認や開発プロセス、費用の透明性、アフターサービスなど、いくつかの重要なポイントがあります。このセクションでは、それぞれのポイントについて詳しく解説します。
実績の確認
実績の確認は、信頼できる開発会社を選ぶための重要なステップです。過去のプロジェクト事例をチェックし、同様の規模や業界での成功実績があるかを確認しましょう。
また、顧客からのフィードバックやレビューも参考になります。実績の豊富な会社は、技術力や対応力に優れており、プロジェクトの成功確率を高めることができます。
開発プロセスとコミュニケーション体制
開発プロセスとコミュニケーション体制の確認は、プロジェクトの進行を円滑にするために重要です。
開発会社がどのような開発プロセスを採用しているか、進捗管理や品質管理の方法を把握しましょう。また、定期的なミーティングや報告の体制が整っているか、クライアントとのコミュニケーションがスムーズに行われるかも確認します。これにより、プロジェクトの透明性と効率が向上します。
開発費用と契約条件の透明性
開発費用と契約条件の透明性は、予算管理と信頼関係の構築に不可欠です。見積もりの詳細が明確に提示されているか、追加費用が発生する可能性やその条件について確認しましょう。
また、契約には変更管理や追加作業に関する条項が含まれていることを確認します。これにより、予期せぬコスト増加や契約トラブルを防ぎ、プロジェクトを円滑に進めることができます。
アフターサービスの確認
アフターサービスの確認は、システム稼働後の安心感を得るために重要です。開発後の保守・サポート体制が整っているかを確認しましょう。
特に、トラブル発生時の対応スピードやサポートの質が重要です。また、定期的なメンテナンスやアップデートの提供、将来的なシステム拡張への対応も確認することが大切です。これにより、システムの長期的な安定運用が保証されます。
発注先の選び方の詳しい情報に関してはこちらの記事にて紹介しておりますので、併せて参考にしてください!
まとめ
今回の記事では、スクラッチ開発について詳しく解説してきました。スクラッチ開発は、企業の特定のニーズやビジネスプロセスに完全に適合するシステムをゼロから構築する手法です。その結果、独自性の高いシステムを実現し、長期的な運用や将来的な拡張に対応できます。
しかし、コストや開発期間が長くなるため、予算や納期に余裕があり、コア業務に直結するプロジェクトに適しています。一方、パッケージ開発は迅速な導入が可能で、費用を抑えられるメリットがありますが、カスタマイズ性に限界があります。
発注先を選ぶ際には、実績の確認、開発プロセスとコミュニケーション体制、費用と契約条件の透明性、アフターサービスを重視しましょう。
スクラッチ開発に関するご相談やご質問がございましたら、ぜひお気軽に弊社、株式会社SALTOまでお問い合わせください。私たちの経験豊富なチームが、最適なソリューションをご提案し、貴社のビジネスを成功に導くお手伝いをいたします!
Illustration by Storyset

この記事の著者
井上雄太
株式会社SALTOにWebエンジニアとして新卒入社。エンジニアとしてWebアプリ開発の業務を経験したのちにマーケティング職に転向。記事のライティングやSNS運用業務を担当。