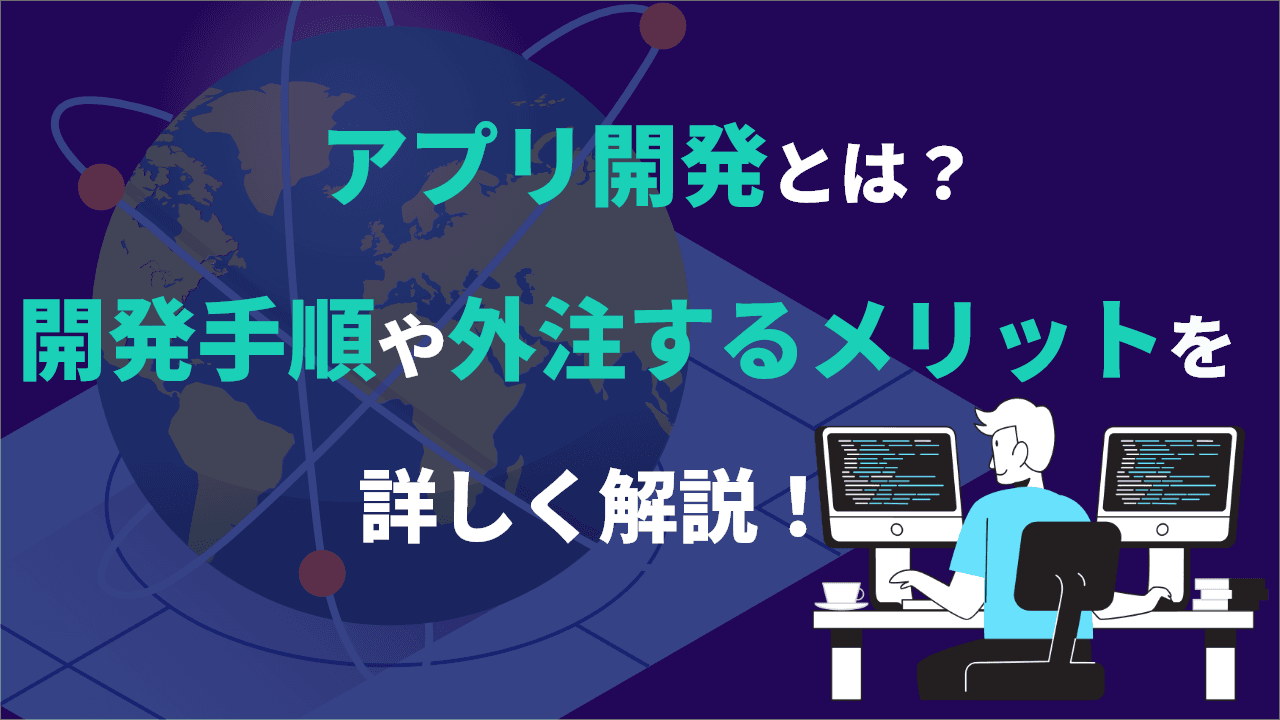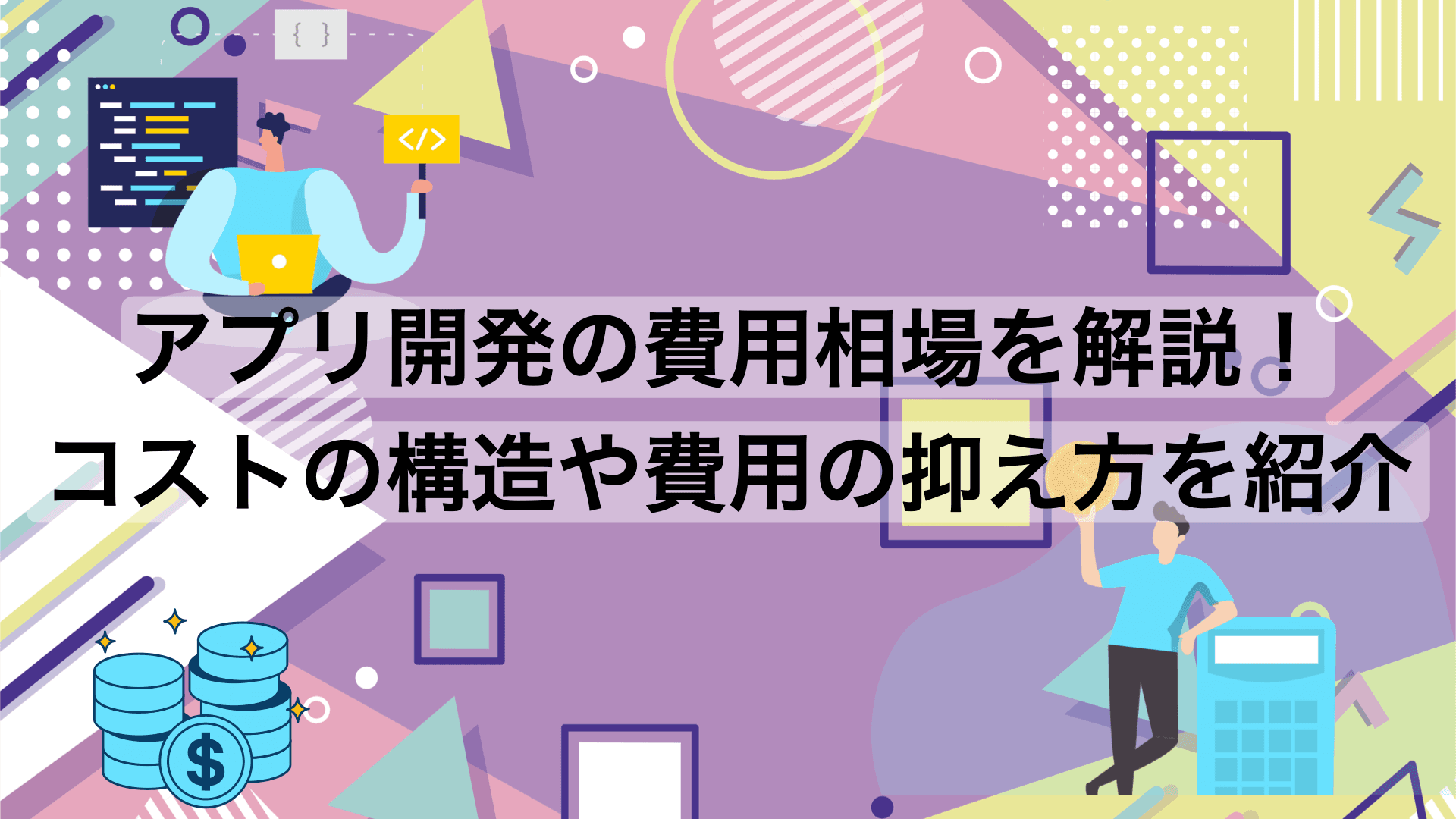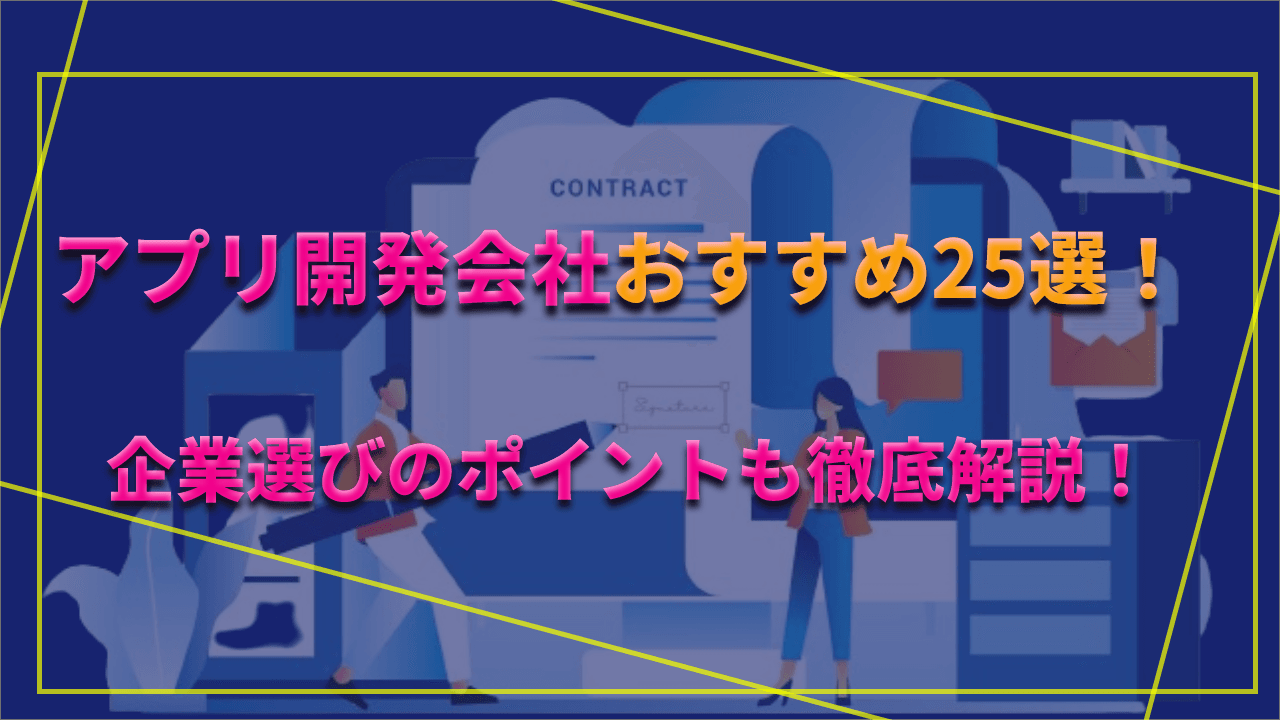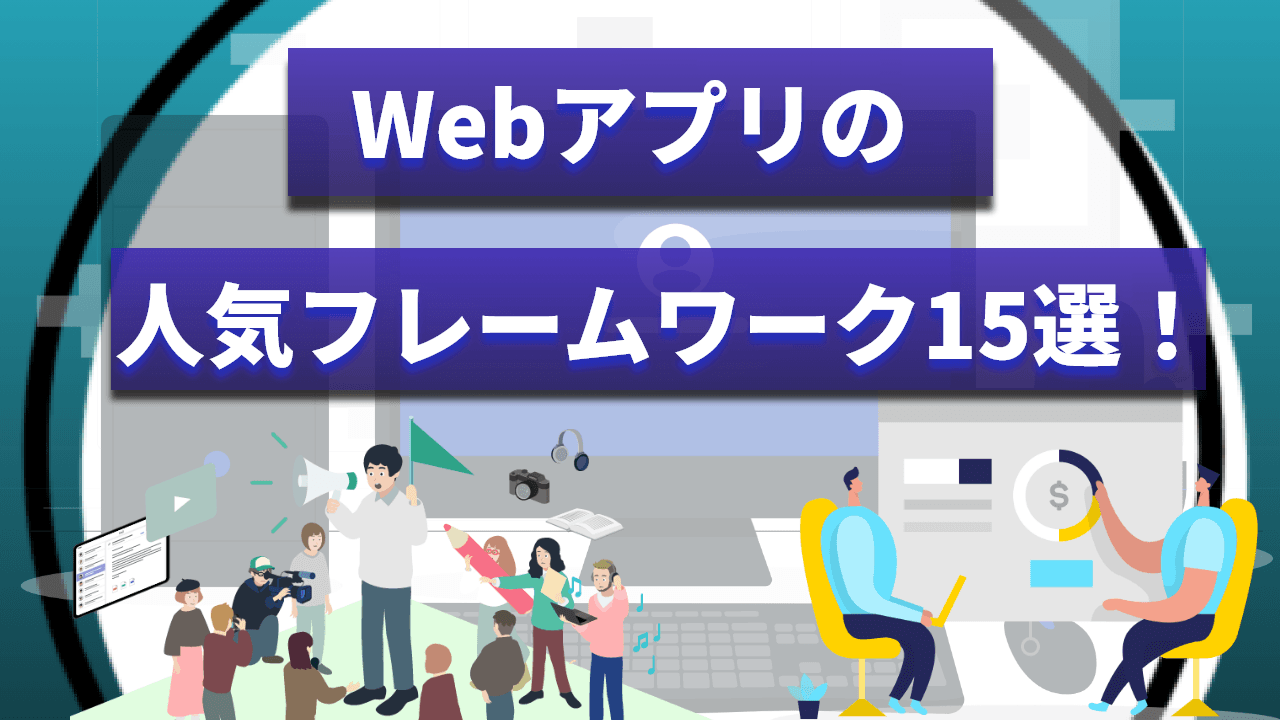【2024年版】システム・アプリ開発時に申請可能な補助金まとめ

あらゆるもののDX化が進む中、新たにシステムやアプリ開発を行いたいと考える機会が増えてきていると思います。システム・アプリ開発に取り組む際、資金調達は常に懸念事項です。
しかし、補助金の情報は日々変化し、古くなりやすいもの。また、申請手続きが煩雑だったり、条件が厳しすぎる場合もあります。
そこでこの記事では、2024年版のシステム・アプリ開発に関する補助金情報を詳しく解説しています。各補助金の種類や申請条件、注意点を一挙に紹介し、ビジネスの成功に役立てるための手助けをいたします。補助金の活用に関する悩みや疑問を解消し、効果的な資金調達の方法をご提供します。この情報を踏まえて、ビジネスの発展にご活用ください。
システム・アプリ開発で活用できる補助金・助成金とは?
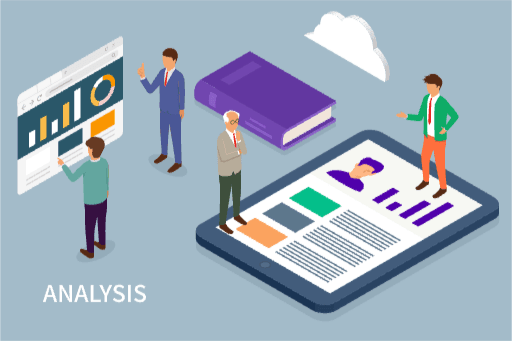
システムやアプリ開発には多くの費用がかかりますが、補助金や助成金を上手に活用すれば、その負担を軽減できます。
まずは、補助金と助成金の違いは何か、またシステムやアプリ開発時に活用できる補助金制度にはどんな種類があるのかを紹介します。
そもそもアプリ開発って?という方は、下記の記事をご覧ください。
アプリ開発にかかる費用について詳しく知りたい方は下記記事をご覧ください。
補助金とは?
補助金は、政府や自治体が特定の目的や活動に対して、財政支援を行う制度です。
補助金を管轄しているのは経済産業省や経済産業省が管轄している独立行政法人などです。また、経済産業省の他にも民間団体により補助金など様々な補助金が存在します。
これにより、特定の産業や分野の発展を促進し、経済の活性化や社会的な課題の解決を図ることが目的です。システムやアプリの開発においても、新しい技術の導入やイノベーションの推進、地域経済の振興などの目的で補助金が提供されることがあります。
補助金の受給には、申請条件や支給条件があり、それらを満たすことで支援を受けることができます。補助金の給付額は数百万円から数十億のものもあります。補助金の採択率は補助金の種類によっても異なりますが、5%から45%前後になっています。
制度の変化により、補助金の内容や条件は常に変動するため、最新の情報を把握することが重要です。
また、補助金は原則後払い(清算払い)になるのでシステムやアプリ開発を発注する際にはキャッシュが必要になります。通常半年から1年後にお金が返ってくる仕組みになっています。
補助金は通年で受け付けられているものではなく、1週間から1ヶ月ほどの期間を設けて公募される仕組みになっています。なので、対象となる期間に合わせて申請準備をする必要があります。

開発オクトパス
助成金とは?
助成金は、国が定めた政策目標に沿うべく行う労働環境の改善などに対して支給されるお金です。
具体的には、雇用の維持のための新規/中途雇用や人材育成、障害者雇用などの目的のために活用されます。
先ほど記載した補助金は経済産業省に管轄されていましたが、助成金は厚生労働省の管轄となります。
国が行う助成金は雇用の定着を目的としていることから、利用できるのは従業員を雇用している雇用保険の適用事業に限られます。
助成金は補助金とは異なり、要件を満たせば受給できる可能性が非常に高い(原則受給可能)制度となっています。受給できる可能性は高いですが、給付額は補助金と比べると低い傾向にあり数十万円から数百万円が目安になっています。

開発オクトパス
システム・アプリ開発で活用できる補助金制度
システムやアプリの開発における補助金制度は多岐にわたります。その中でも活用しやすいのは次の3つの制度です。
まず1つ目は「ものづくり補助金」です。「ものづくり補助金」は新事業や新製品に伴う機械装置/システム開発が対象となる補助金制度です。
2つ目は「IT導入補助金」です。「IT導入補助金」は業務効率化やDX化に向けたシステム導入が対象となる補助金制度です。「IT導入補助金」において対象となるシステムは既製品のシステムが対象となるため、新規でゼロから開発するシステムは対象外となっています。
そして3つ目は、「事業再構築補助金」です。「事業再構築補助金」は新事業に伴う業種転換や新分野進出を行う際のシステム開発や建物費、広告費などが対象となっています。
この3つの制度以外にも、「躍進的な事業推進のための設備支援支援事業」や「小規模事業者持続化補助金」、「経営革新計画」なども、アプリ開発における資金調達や経営改善に役立つ制度です。
次のセクションからはこれらの制度について詳しく紹介していきます。
ものづくり補助金
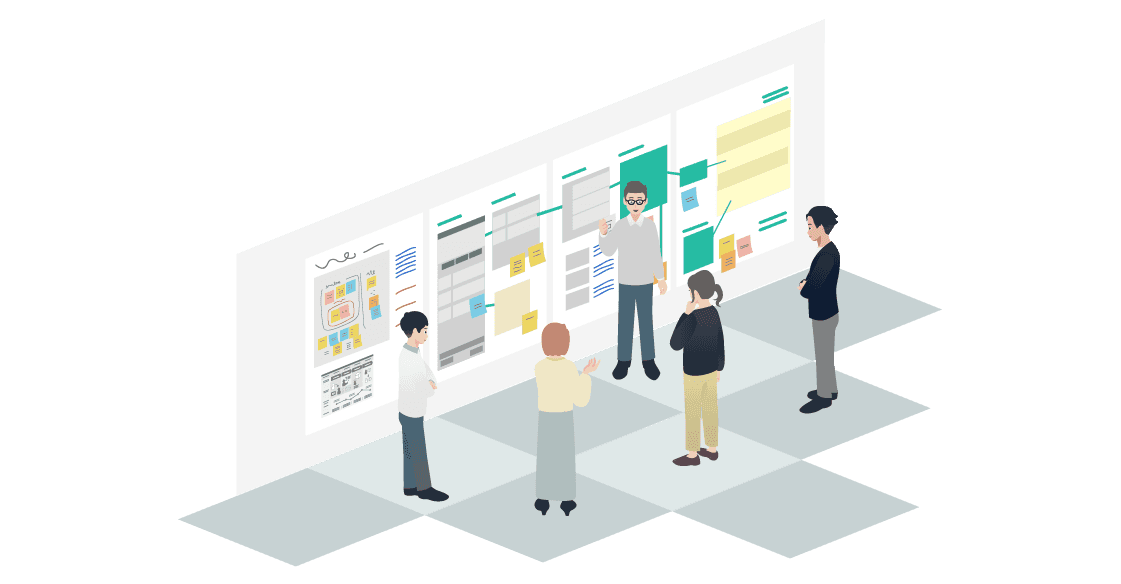
制度の概要 -ものづくり補助金-
「ものづくり補助金」の正式名称は「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金となっており、生産性向上に向けた革新的製品/サービスの開発や、生産プロセスなどの改善に必要な設備投資などを支援するための補助金となっています。
また、「ものづくり補助金」には「通常枠」、「回復型賃上げ雇用拡大枠」、「デジタル枠」、「グリーン枠」、「グローバル市場開拓枠」の5つの申請枠があります。それぞれの申請枠の概要は次の通りです。
| 申請枠 | 概要 |
|---|---|
| 通常枠 | 革新的な製品・サービス開発又は⽣産プロセス・サービス提供方法の改善に必要な設備・システム投資等を支援 |
| 回復型賃上げ雇用拡大枠 | 業況が厳しい事業者が賃上げ・雇用拡大に取り組むための事業であれば申請可能 |
| デジタル枠 | システム開発などDXに資する取り組みであれば申請可能 |
| グリーン枠 | 温室効果ガスの排出削減に資する取り組みであれば申請可能 |
| グローバル市場開拓枠 | 海外事業の拡大等を目的とした設備投資等・海外展開に資する取り組みであれば申請可能 |
制度の対象 -ものづくり補助金-
「ものづくり補助金」の対象となるのは、中小企業や小規模事業者です。特に製造業やものづくりに関わる企業が主な対象とされています。
業種によって対象となる事業者が異なり、資本金額と従業員数の2つの項目に基準が設けられています。
例えば、製造業を行っている中小企業の場合、資本金額が3億円以下もしくは従業員数が300人以下、卸売業を行っている中小企業の場合、資本金額が1億円以下、もしくは従業員数が100人以下、サービス業を行っている中小企業の場合、資本金額5000万円以下、もしくは従業員数100人以下といった条件が課せられています。
申請条件 -ものづくり補助金-
「ものづくり補助金」を申請するには、条件があり、次の3つの要件全てを満たす3年から5年の事業計画を策定し、従業員に表明している必要があります。
1.事業者全体の付加価値額を年率平均3%以上増加
※付加価値額・・・営業利益、人件費、減価償却費の合計
2.給与支給総額を年率平均1.5%から3%以上増加
※給与支給総額・・・全従業員(非常勤含む)および役員に支払った給与など
3.事業場内最低賃金を地域別最低賃金+30円から+90円の水準にする
※事業場内最低賃金・・・事業場内で最も低い賃金
例えば、製造業を行っている中小企業の場合、資本金額が3億円以下もしくは従業員数が300人以下、卸売業を行っている中小企業の場合、資本金額が1億円以下、もしくは従業員数が100人以下、サービス業を行っている中小企業の場合、資本金額5000万円以下、もしくは従業員数100人以下といった条件が課せられています。
補助率/補助金額 -ものづくり補助金-
補助率や補助金額は、申請枠の種別や規模によって異なります。
補助率
助率に関しては、申請枠、事業者の規模によって割合が変動します。
具体的な補助率は次の通りです。
| 申請枠 | 補助率 |
|---|---|
| 通常枠 | 1/2 ※小規模事業者は2/3 |
| 回復型賃上げ雇用拡大枠 | 2/3 |
| デジタル枠 | 2/3 |
| グリーン枠 | 2/3 |
| グローバル市場開拓枠 | 1/2 ※小規模事業者は2/3 |
補助金額
補助額はそれぞれの申請枠ごとの従業員数によって上限額が変動します。
具体的な補助金額は次の通りです。
| 申請枠 | 補助率 |
|---|---|
| 通常枠 回復型賃上げ雇用拡大枠 デジタル枠 | 5人以下 100〜750万円 6〜20人 100〜1,000万円 21人以上 100〜1,250万円 |
| グリーン枠 | エントリー類型 750万円〜1,000万円 スタンダード類型 1,000万円〜2,000万円 アドバンス類型 2,000万円〜4,000万円 |
| グローバル市場開拓枠 | 1,000万円〜3,000万円 |
IT導入補助金
制度の概要 -IT導入補助金-
「IT導入補助金」は、中小企業・小規模事業者等の労働生産性向上を目的とした制度です。この制度を活用することによって、ITツールの導入を支援し課題解決へ導くことを目的としています。
「IT導入補助金」には、「通常枠」、「インボイス枠(インボイス対応類型)」、「インボイス枠(電子取引類型)」、「セキュリティ対策推進枠」、「複数社連携IT導入枠」の5つの申請枠があります。それぞれの申請枠の概要は次の通りです。(抜粋元:https://it-shien.smrj.go.jp/)
| 申請枠 | 概要 |
|---|---|
| 通常枠 | 自社の課題にあったITツールを導入し、業務効率化・売上アップをサポート |
| インボイス枠 (インボイス対応類型) | インボイス制度に対応した会計ソフト、受発注ソフト、 決済ソフトに特化し労働生産性の向上をサポート |
| インボイス枠 (電子取引類型) | インボイス制度に対応した受発注システムを商流単位で導入する企業を支援 |
| セキュリティ対策推進枠 | サイバー攻撃の増加に伴う潜在的なリスクに対処するため、 サイバーインシデントに関する様々なリスク低減策を支援 |
| 複数社連携IT導入枠 | 業務上つながりのある「サプライチェーン」や、 特定の商圏で事業を営む「商業集積地」に属する複数の 中小企業・小規模事業者等が連携してITツールを導入し、生産性の向上を図る取り組みを支援。 |
制度の対象 -IT導入補助金-
「IT導入補助金」の対象となるのは、中小企業や小規模事業者です。
業種によって対象となる事業者が異なり、資本金額と従業員数の2つの項目に基準が設けられています。
例えば、製造業を行っている中小企業の場合、資本金額が3億円以下もしくは従業員数が300人以下、卸売業を行っている中小企業の場合、資本金額が1億円以下、もしくは従業員数が100人以下、サービス業を行っている中小企業の場合、資本金額5000万円以下、もしくは従業員数100人以下といった条件が課せられています。
また、医療法人・社会福祉法人・学校法人は従業員数が300人以下であれば対象となります。
申請条件 --IT導入補助金-
「IT導入補助金」を申請するには、条件があり、次の3つの要件を満たす必要があります。ただし、申請枠の種別によっては不要のケースがあります。
1.gBizIDプライムの取得
※複数社連携IT導入枠の「参画事業者」はgBizIDの取得は不要です。
2.SECURITY ACTION
3.「みらデジ経営チェック」 ※通常枠でのみ「みらデジ経営チェック」の実施が必要となります。
補助率/補助金額 -IT導入補助金-
補助率や補助金額は、申請枠の種別や規模によって異なります。
補助率
補助率に関しては、申請枠、事業規模、使用用途によって変動します。
具体的な補助率は次の通りです。
| 申請枠 | 補助率 |
|---|---|
| 通常枠 | 1/2以内 |
| インボイス枠 (インボイス対応類型) | 【会計・受発注・決済のうち1機能以上】 :中小企業は3/4、小規模事業者は4/5 【会計・受発注・決済のうち2機能以上】 :50万円超~350万円以下の部分の補助率は2/3。 (補助額のうち50万円以下の部分については①と同じく 中小企業は3/4、小規模事業者は4/5) 【PC/ハードウェアなど】 1/2以内 |
| インボイス枠 (電子取引類型) | 【中小企業/小規模事業者等】 2/3以内 【その他事業者等】 1/2以内 |
| セキュリティ対策推進枠 | 1/2以内 |
| 複数社連携IT導入枠 | 【基盤導入経費-ソフトウェア】 3/4以内、4/5以内※ 【基盤導入経費-ソフトウェア】 2/3以内※ ※補助額のうち50万円以下については補助率は3/4以内(ただし、小規模事業者は4/5以内)、 50万円超については補助率は2/3以内。 【基盤導入経費-ハードウェア-PC・タブレット等】 1/2以内 【基盤導入経費-ハードウェア-レジ・発券機等】 1/2以内 【消費動向等分析経費】 2/3以内 【その他経費】 2/3以内 |
補助金額
補助額はそれぞれの申請枠ごとの業務プロセスの数、使用用途などによって上限額が変動します。
具体的な補助金額は次の通りです。
| 申請枠 | 補助金額 |
|---|---|
| 通常枠 | 【1プロセス以上】 5万円以上150万円未満 【4プロセス以上】 150万円以上450万円以下 |
| インボイス枠 (インボイス対応類型) | 【会計・受発注・決済のうち1機能以上】:50万円以下 【会計・受発注・決済のうち2機能以上】:50万円超~350万円以下 【PC/ハードウェアなど-PC・タブレット等】 10万円以下 【PC/ハードウェアなど-レジ・発券機等】 20万円以下 |
| インボイス枠 (電子取引類型) | 下限なし〜350万円以下 |
| セキュリティ対策推進枠 | 5万円以上100万円以下 |
| 複数社連携IT導入枠 | 【基盤導入経費-ソフトウェア】 50万円以下×グループ構成員数 【基盤導入経費-ソフトウェア】 50万円超〜350万円以下×グループ構成員数 【基盤導入経費-ハードウェア-PC・タブレット等】 10万円以下×グループ構成員数 【基盤導入経費-ハードウェア-レジ・発券機等】 20万円以下×グループ構成員数 【消費動向等分析経費】 50万円以下×グループ構成員数 【その他経費】 200万円以下(補助額上限は【基盤導入経費と消費動向等分析費の合計額】×10%×2/3(補助率)もしくは200万円のいずれか小さい額) ※基盤導入経費と消費動向分析経費の合計額は3000万円が上限 |
事業再構築補助金
制度の概要 -事業再構築補助金-
「事業再構築補助金」は、コロナの影響で厳しい状況にある中小企業、中堅企業、個人事業主などを対象とした支援制度です。
また、「事業再構築補助金」には、「成長枠」、「最低賃金枠」、「物価高騰対策・回復再生応援枠」、「産業構造転換枠」、「グリーン成長枠」、「サプライチェーン強靭化枠」の6つの申請枠があります。それぞれの申請枠の概要は次の通りです。
| 申請枠 | 概要 |
|---|---|
| 成長枠 | 成長分野への大胆な事業再構築に取り組む事業者を支援 |
| 最低賃金枠 | 最低賃金引上げの影響を受け、その原資の確保が困難な特に業況の厳しい中小企業等の事業再構築を支援 |
| 物価高騰対策・回復再生応援枠 | 業況が厳しい事業者や事業再生に取り組む事業者原油価格・物価高騰等の影響を受ける事業者 |
| 産業構造転換枠 | 国内市場縮小等の構造的な課題に直面している業種・業態の事業者 |
| グリーン成長枠 | グリーン成長戦略「実行計画」14 分野の課題の解決に資する取組を行う事業再構築を支援 |
| サプライチェーン強靭化枠 | 海外で製造する部品等の国内回帰を進め、国内サプライチェーンの強靱化及び地域産業の活性化に資する取組を行う事業者 |
制度の対象 -事業再構築補助金-
「事業再構築補助金」の対象となるのは、中小企業や特定事業者です。特に製造業やものづくりに関わる企業が主な対象とされています。
業種によって対象となる事業者が異なり、資本金額と従業員数の2つの項目に基準が設けられています。
例えば、製造業を行っている中小企業の場合、資本金額が3億円以下もしくは従業員数が300人以下、卸売業を行っている中小企業の場合、資本金額が1億円以下、もしくは従業員数が100人以下、サービス業を行っている中小企業の場合、資本金額5000万円以下、もしくは従業員数100人以下といった条件が課せられています。
申請条件 -事業再構築補助金-
「事業再構築補助金」を申請するには、条件があり、次の2つの要件を満たす必要があります。
1.指針にそった3〜5年の事業計画書を認定経営革新等期間と共同で策定。
また、補助金額が3,000万円を超える場合は。認定経営革新等支援機関及び金融機関と策定。
2.補助事業終了後3〜5年で全体(従業員1人当たり)の付加価値額を年率平均3%以上増加
※付加価値額・・・営業利益、人件費、減価償却費の合計額
補助率/補助金額 -事業再構築補助金-
補助率や補助金額は、申請枠の種別や規模によって異なります。
補助率
補助率に関しては、申請枠、事業規模によって変動します。
具体的な補助率は次の通りです。
| 申請枠 | 補助率 |
|---|---|
| 成長枠 | 1/2(大規模賃上げ達成で2/3へ引き上げ) |
| 最低賃金枠 | 3/4 |
| 物価高騰対策・回復再生応援枠 | 2/3(一部3/4) |
| 産業構造転換枠 | 中小企業者等 2/3 中堅企業等 1/2 |
| グリーン成長枠 | 中小企業者等 1/2 中堅企業等 1/3 |
| サプライチェーン強靭化枠 | 中小企業等 1/2 中堅企業等 1/2 |
補助金額
補助額はそれぞれの申請枠ごとに上限額が変動します。
具体的な補助金額は次の通りです。
| 申請枠 | 補助率 |
|---|---|
| 成長枠 | 100万円~7,000万円 |
| 最低賃金枠 | 100 万円~1,500万円 |
| 物価高騰対策・回復再生応援枠 | 100 万円~3,000万円 |
| 産業構造転換枠 | 100万円~1,500万円 中堅企業等 1/2 |
| グリーン成長枠 | 中小企業者等 100万円~1億円 中堅企業等 100万円~1.5億円 |
| サプライチェーン強靭化枠 | 100万円~5億円 |

開発オクトパス
その他の補助金

躍進的な事業推進のための設備支援支援事業
「躍進的な事業推進のための設備支援支援事業」は、市場の拡大が期待される産業分野におけるDXの推進を目的とし、機械設備や器具備品、ソフトウェアの購入経費の一部を助成する制度です。
制度の対象となる企業は、東京都内に登記簿上の本店または支店があり、都内で2年以上事業を継続している中小企業等です。
対象となる事業については、次の4つのどれかに該当している必要があります。
・競争力・ゼロエミッション強化
・DX促進
・イノベーション
・後継者チャレンジ
支給額は3,000万円〜1億円となっており、高額な支援を受けることができます。
「躍進的な事業推進のための設備支援支援事業」を受給するには、「ものづくり補助金」などとは異なり、書類審査の他に面接審査がある点にも注意が必要です。
過去の「躍進的な事業推進のための設備支援支援事業」の採択率は令和2年度が約40%、令和3年度が約25%、令和4年度が約40%になっています。
小規模事業者持続化補助金
「小規模事業者持続化補助金」は、中小企業や個人事業主に向けた補助金制度で、中小企業庁監督のもと日本商工会議所と商工会が管轄となっているものです。
制度の対象となるのは、小規模事業者と要件を満たしたNPO法人となっています。
※小規模事業者・・・商業・サービス業は5名以下、宿泊業・娯楽業、製造業・その他は20名以下
「小規模事業者持続化補助金」には、一般型と低感染リスク型ビジネス枠があり、一般型では補助上限金額50万円、補助率2/3、低感染リスクビジネス枠では補助上限100万円、補助率3/4となっています。
過去の「小規模事業者持続化補助金」の採択率は、第3回が51.6%、第4回が44.2%、第5回が53.9%となっています。
補助金を活用する際に気を付けたいポイント
補助金を活用する際には、様々なポイントに留意することが肝要です。以下に、そのポイントを詳細に解説します。
採択されない失敗例を把握しておく
補助金の申請において、採択されない失敗例を把握することは非常に重要です。過去の事例や他社の経験を参考にすることで、申請書類の作成や申請内容の検討に役立ちます。また、失敗例を把握することで、同様の失敗を避けることができます。
補助金が採択された同業種の例を把握しておく
補助金が採択された同業種の例を把握することは、有益な情報収集手段です。他社の事例を参考にすることで、成功事例やベストプラクティスを学ぶことができます。
また、同業種の例を把握することで、自社の補助金申請における戦略やアプローチを検討することができます。
提出書類の徹底管理
補助金の申請に必要な提出書類は多岐にわたります。
これらの書類を徹底的に管理することは欠かせません。提出期限や必要書類の内容、フォーマットなどを正確に把握し、適切な管理体制を整えることが重要です。また、必要書類の提出漏れや不備を事前に防ぐために、十分な準備と確認が必要です。
適切な事務処理を行っていない場合、補助金を受け取れないケースも発生するため徹底した管理を行いましょう。
補助金採択スケジュールの確認
補助金の採択までのスケジュールは、申請者にとって重要な要素です。
採択までの期間や各段階の審査手続き、結果発表のタイミングなどを把握し、スケジュール通りに申請作業を進めることが求められます。また、採択された場合の支給時期も考慮し、経営計画や資金調達計画を立てる必要があります。
申請した事業期間外に発生した経費は経費として認められないので、スケジュール通りに事業を進めることはとても重要になります。
補助金の受給時期
補助金は後払いされるため、企業は投資を行った後に補助金を受け取ります。そのため、投資に必要な資金はあらかじめ別に調達する必要があります。
採択後、事業完了後に補助金を受け取るまでの間には「つなぎ融資」という制度があります。これは、金融機関が採択者に対して融資を行い、補助金事業が円滑に進むよう支援します。補助金の受給には計画と資金計画が必要です。
補助金の申請を代行業者に依頼する場合について
補助金の申請を代行業者に依頼する場合、様々なメリットやデメリットがあります。また、適切な代行業者を選ぶことも重要です。以下に、それぞれのポイントについて詳しく解説します。
申請を代行業者に依頼するメリット
補助金の申請を代行業者に依頼することには、次のようなメリットがあります。
専門知識の活用: 代行業者は補助金申請に関する専門知識を有しており、申請書類の作成や手続きの遂行において効率的かつ正確なサポートを提供してくれます。
煩雑な手続きの軽減: 補助金の申請手続きは煩雑であり、多くの企業や個人事業主にとって負担が大きいものです。代行業者に依頼することで、手続きの負担を軽減することができます。
成功率の向上: 代行業者は過去の経験やノウハウを活かして、補助金の申請において成功率を高めることができます。適切な戦略やアプローチを提案し、申請の成否に大きく影響を与えます。
申請を代行業者に依頼するデメリット
一方で、補助金の申請を代行業者に依頼することには、次のようなデメリットも考えられます。
費用の負担: 代行業者に依頼する場合、そのサービスに対する費用が発生します。この費用は補助金の額によって変動しますが、申請者にとっては追加の負担となります。
情報の制御: 代行業者に依頼することで、申請者は一部の情報を代行業者に開示する必要があります。これにより、申請者の情報が外部に漏れるリスクが生じる可能性があります。
信頼性の問題: 代行業者の中には信頼性の低い業者も存在し、そのような業者に依頼すると申請の手続きが遅延したり、不正確な情報が提出されるなどの問題が発生する可能性があります。
申請代行会社の選び方
補助金の申請代行会社を選ぶ際には、次のポイントに注意することが重要です。
専門性と実績: 代行会社の専門性や実績を確認し、補助金申請における成功事例や評判を調査しましょう。
費用と契約内容: 代行会社の費用体系や契約内容を明確に把握し、不明確な点や隠れた費用がないかを確認しましょう。
信頼性と信用度: 代行会社の信頼性や信用度を調査し、信頼できる会社であるかを確認しましょう。
申請代行の相場
補助金の申請代行の相場は様々ですが、一般的には補助金の額や申請内容によって異なります。
相場を把握するためには、複数の代行会社の料金を比較し、適切な価格設定を選択することが重要です。また、料金の明確化や支払い条件の確認も忘れずに行うことが大切です。
多くの場合、申請代行の費用は「着手金」と「成功報酬」に別れています。
着手金の相場がおよそ10万円から15万円、成功報酬の相場が5%から15%となっています。
まとめ
システム・アプリ開発において補助金は重要な資金調達手段の1つになります。補助金を活用することで、システムやアプリの開発に必要な資金を調達しやすくなり、新規事業の立ち上げや既存事業の拡大に向けた取り組みを支援します。
それぞれの補助金制度には対象となる事業や申請条件、補助金の額や補助率などが異なりますが、適切に活用することでアプリ開発プロジェクトの資金調達に役立ちます。
株式会社SALTOでは、補助金の採択支援からシステムやアプリの開発、運用までワンストップで対応しております。
補助金活用とオフショア開発を組み合わせて大幅なコストカットも可能となりますので、ご興味ある方はご連絡お待ちしております。
アプリ開発会社をお探しの方は、こちらの記事もご覧ください!

この記事の著者
中島 彩
株式会社SALTOに営業職として入社後、WEBマーケティング職にキャリアチェンジ。コンテンツディレクター業務からライティング業務まで一貫して対応。自社のシステム開発のノウハウを取り入れた記事を執筆中。