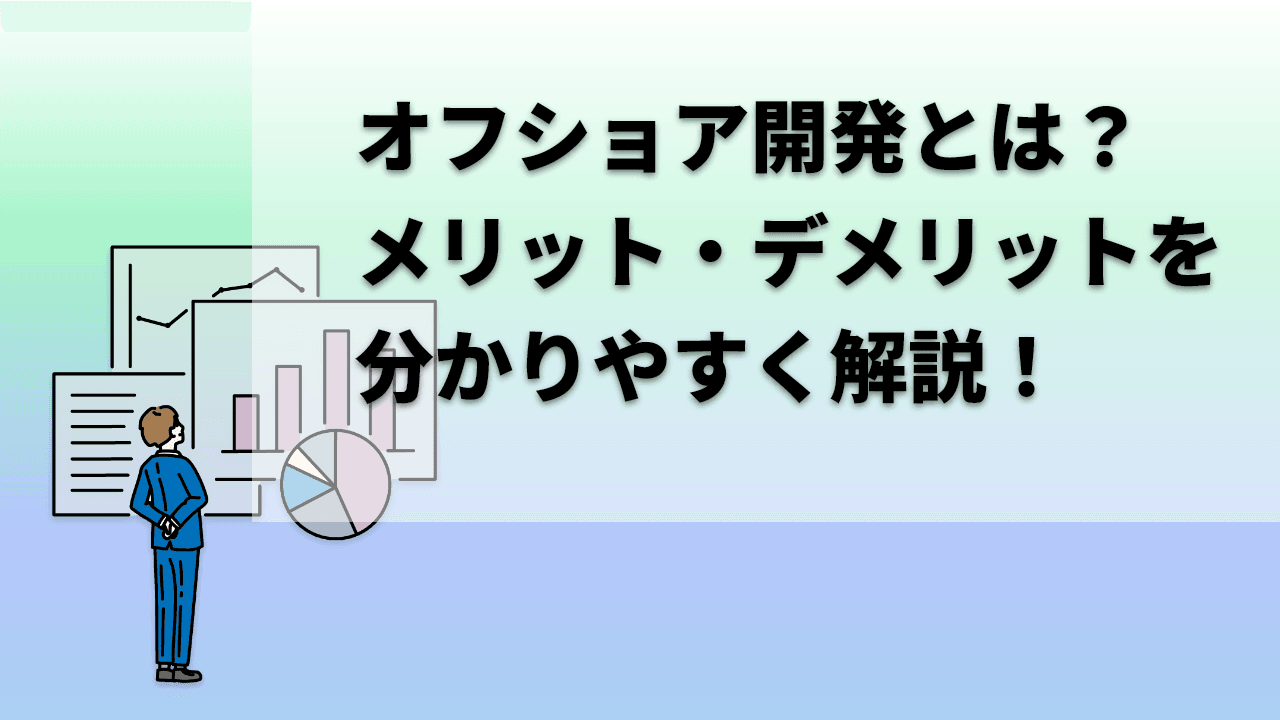システムリプレイスとは?進め方やメリット、移行方法を解説
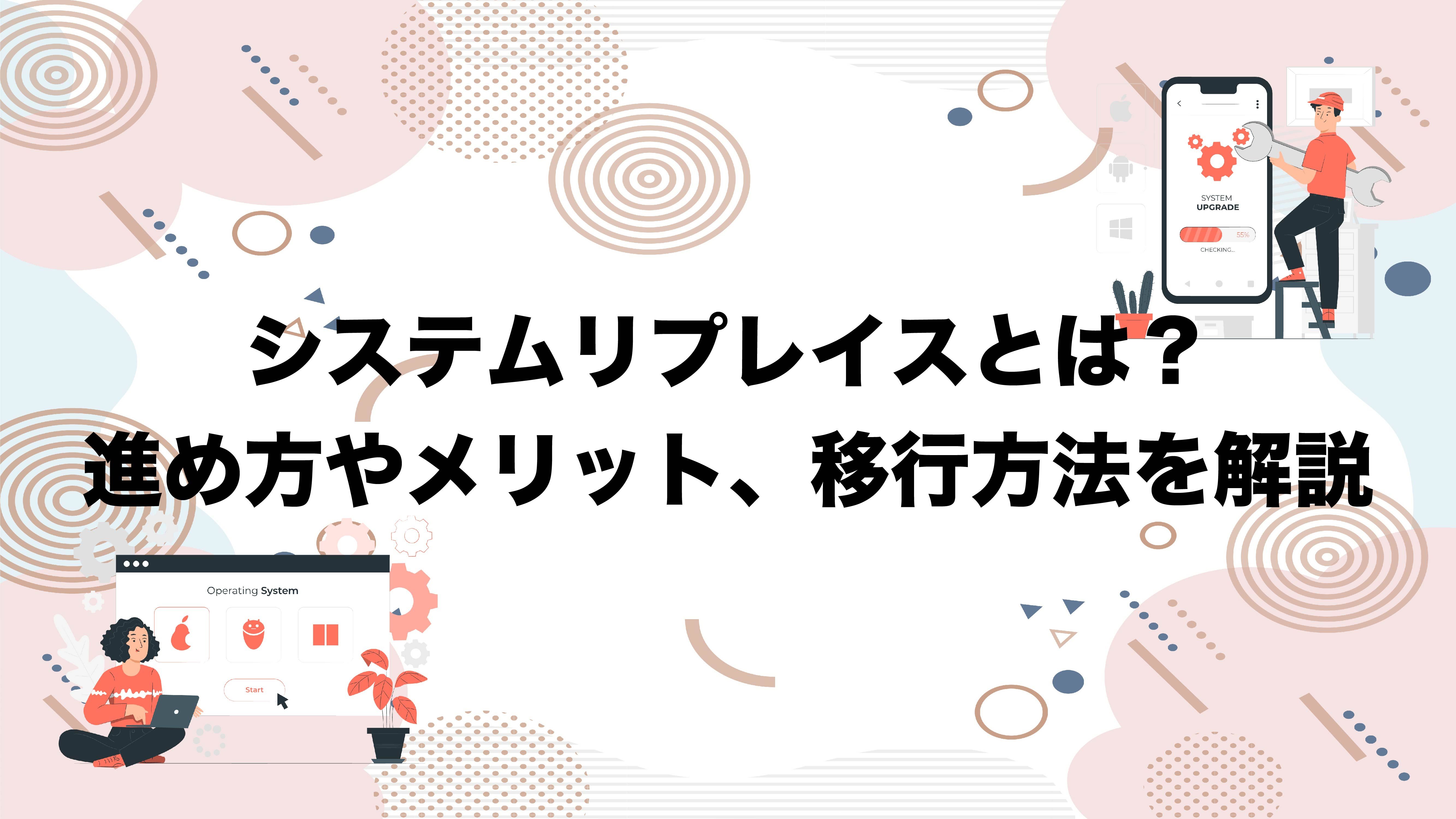
システムリプレイスは、企業が成長し続けるために欠かせないプロセスです。古くなったシステムを最新技術へと刷新することで、業務効率化やコスト削減、セキュリティの向上など多くのメリットを享受できます。
しかし、リプレイスには大きな投資やリスクが伴い、適切な方法で進めないと、業務停止やデータの紛失といった深刻な問題が発生することもあります。
本記事では、システムリプレイスの基本概要から進め方、メリット・デメリット、移行方法を詳しく解説し、成功のためのポイントも紹介します。これからシステムリプレイスを検討している企業の皆様にとって、実践的で役立つ情報を提供します。
システムリプレイスとは?
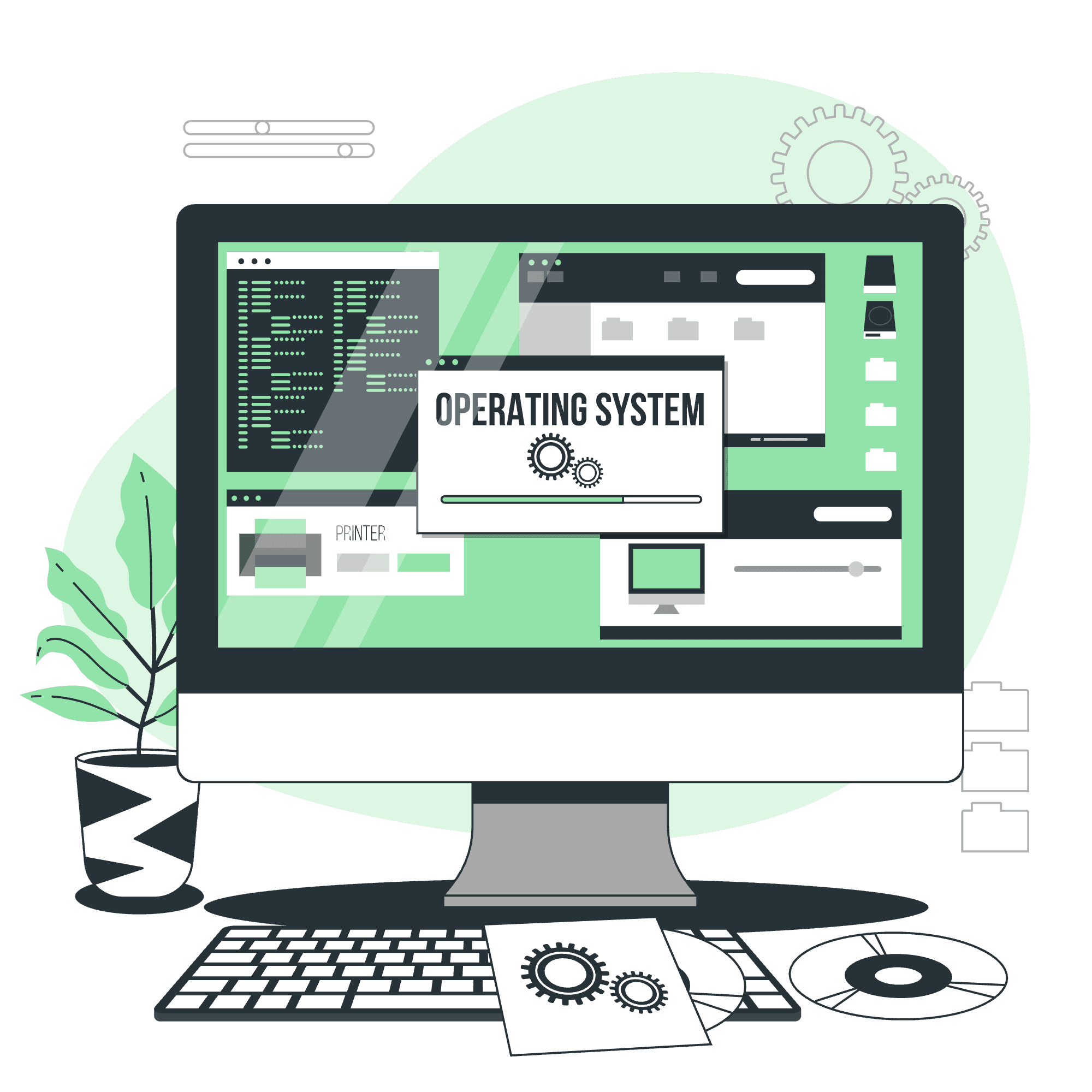
システムリプレイスは、古いシステムを最新技術に置き換えるプロセスです。このセクションでは、リプレイスの概要、マイグレーションとの違い、リプレイスが必要な理由や適切なタイミングについて解説します。企業が効率的にシステムを刷新するためのポイントを紹介します。
システムリプレイスの概要
システムリプレイスとは、 現行の古いシステムを新しい技術やプラットフォームに置き換えるプロセスのことです。
システムが古くなると、セキュリティリスクが高まり、業務効率が低下するなどの問題が発生します。これらの問題を解決し、最新の技術を活用するために、システム全体を刷新する必要があります。
リプレイスは単なるシステムのアップデートではなく、業務プロセスの見直しや改善も伴うことが多く、企業の競争力を高め、ビジネスの成長をサポートします。リプレイスは、システムの長期的な運用を見据えた重要な投資であり、現代のビジネス環境において不可欠な取り組みとなっています。
システムリプレイスとマイグレーションの違いとは?
システムリプレイスとマイグレーションは、どちらもシステムの移行プロセスを指しますが、その範囲と目的に違いがあります。
システムリプレイスは、既存システムを新しい技術やプラットフォームに全面的に置き換えることを意味し、機能や構造を大幅に変更することが多いです。
一方、マイグレーションは、システムのデータやアプリケーションを別の環境に移行する作業で、システム自体の構造はあまり変更されません。リプレイスは業務改革を伴うことが多く、マイグレーションは現状を維持しつつ移行するケースが多いです。
システムリプレイスが必要な理由
システムリプレイスが必要となる主な理由は、現行システムが時代遅れとなり、企業の成長や効率化を妨げる場合です。
古いシステムでは、最新技術への対応が難しく、セキュリティリスクが高まる可能性があります。また、システムのパフォーマンスが低下し、業務が円滑に進まなくなることもあります。
さらに、保守・運用コストが年々増加し、システム維持が経済的に非効率となることから、最新技術を取り入れて長期的な競争力を確保するために、システムリプレイスが求められるのです。
システムリプレイスを行う時期
システムリプレイスを行う適切な時期は、一般的にシステム導入後5~10年が目安とされています。技術の進化が急速に進む現代では、5年程度で新しい技術やトレンドに対応する必要が生じることが多いです。
特に、システムのパフォーマンス低下や操作の遅延、頻繁なエラーが発生するようになった場合は、リプレイスのサインです。また、セキュリティ面でも脆弱性が増すため、古いシステムでは最新のセキュリティ基準に対応できないことが増えてきます。
さらに、保守費用が高騰し、コストパフォーマンスが低下した場合も、リプレイスを検討するタイミングです。企業の成長や業務変革に伴い、システムの柔軟性が不足した際にも、適切な時期といえるでしょう。
システムリプレイスを行うメリットとデメリット
システムリプレイスには、最新技術の導入やセキュリティの強化など、多くのメリットがあります。しかし、一方で初期費用が高額になったり、移行中の業務停止リスクなど、デメリットも伴います。このセクションでは、システムリプレイスを行う際の具体的なメリットとデメリットについて詳しく解説します。システム刷新を成功させるためには、これらの要素をしっかりと理解し、適切に対応することが重要です。
システムリプレイスを行うメリット
最新技術導入による性能向上
システムリプレイスにより、最新の技術やプラットフォームを導入することで、システムのパフォーマンスが大幅に向上します。特に、古いシステムでは処理速度や拡張性が限られているため、最新技術を導入することでデータ処理やアプリケーションの応答速度が飛躍的に改善されます。
さらに、クラウド技術やAI、IoTなどの先進技術を活用することで、業務プロセスを自動化したり、より効率的な運用が可能となります。これにより、業務の柔軟性が高まり、企業全体のパフォーマンス向上に寄与します。
セキュリティ強化
古いシステムは、セキュリティの脆弱性が高く、サイバー攻撃やデータ漏洩のリスクが増大します。システムリプレイスを行うことで、最新のセキュリティ技術や対策を導入し、セキュリティレベルを飛躍的に向上させることができます。
例えば、データ暗号化、二要素認証、脆弱性管理などの最新セキュリティ機能を取り入れることで、外部からの攻撃リスクを大幅に軽減できます。セキュリティの強化は、企業の信頼性を維持し、顧客情報や機密データを安全に守るために不可欠な取り組みです。
メンテナンスコストの削減
古いシステムを維持するための保守や運用コストは、年々高くなる傾向にあります。システムリプレイスにより、最新の技術やインフラに移行することで、メンテナンスや運用にかかるコストを大幅に削減することができます。
最新のシステムは、より効率的でトラブルが少なく、運用の自動化や定期的なアップデートが容易なため、保守費用が抑えられます。また、システムのダウンタイムが減少するため、修理やサポートにかかる時間や費用も軽減され、トータルコストが削減されます。
業務効率の向上
システムリプレイスにより、企業の業務プロセスを最適化し、効率を大幅に向上させることができます。最新のシステムは、業務プロセスの自動化やデータ処理の高速化を可能にし、従業員が手動で行っていた作業を大幅に削減します。
また、システムの使い勝手が向上することで、業務の迅速な処理が実現し、ミスや遅延を減らすことができます。これにより、従業員の生産性が向上し、企業全体の業務効率が飛躍的に高まるため、競争力の強化にもつながります。
システムリプレイスを行うデメリット
初期費用が高額
システムリプレイスは、多くの場合、初期費用が高額になるのがデメリットです。新しいシステムの導入には、ハードウェアやソフトウェアの購入費用、カスタマイズ費用、そして移行作業にかかるコストが必要です。
また、システム開発や設計、テスト、導入後のサポートなどに関する費用も発生します。特に大規模なシステムリプレイスでは、数千万円から数億円に達することもあり、企業にとって大きな投資が必要となります。短期的なコスト負担が重くなるため、予算確保が課題となることがあります。
リプレイス中の業務停止リスク
システムリプレイス中に業務停止のリスクが生じることも、デメリットの一つです。システムの移行作業中に一時的に業務が止まってしまうと、企業活動に影響を与え、生産性の低下や取引の遅延を招く可能性があります。
また、予期しないトラブルや移行プロセスの遅れが発生すると、システムの稼働開始が予定より遅れることもあります。これにより、業務停止が長引くリスクもあるため、事前に緻密な計画とリスク管理が求められます。
従業員のトレーニングコスト
新しいシステムの導入に伴い、従業員が新しいツールや操作方法に慣れるためのトレーニングが必要となります。従業員は慣れ親しんだシステムから移行するため、操作性や機能に違いがある場合、効率的に新しいシステムを使いこなすためには一定の時間とコストがかかります。
特に、全社的に新システムを導入する場合、トレーニング期間中は業務効率が低下する可能性があります。また、トレーニング自体に外部講師やシステムのサポート費用が発生することもあります。
データ移行時のリスク
システムリプレイスには、既存のデータを新しいシステムに移行する作業が伴いますが、このデータ移行は非常にリスクが高い部分です。移行時にデータが破損したり、欠損したりするリスクがあり、データの完全性や一貫性が損なわれる可能性があります。
特に、大量のデータや複雑なデータベース構造を持つシステムでは、移行作業中に想定外のトラブルが発生しやすくなります。また、移行後にデータの整合性を確保するために追加作業が必要になることもあり、時間とコストが増大することもデメリットです。

開発オクトパス
システムリプレイスの進め方
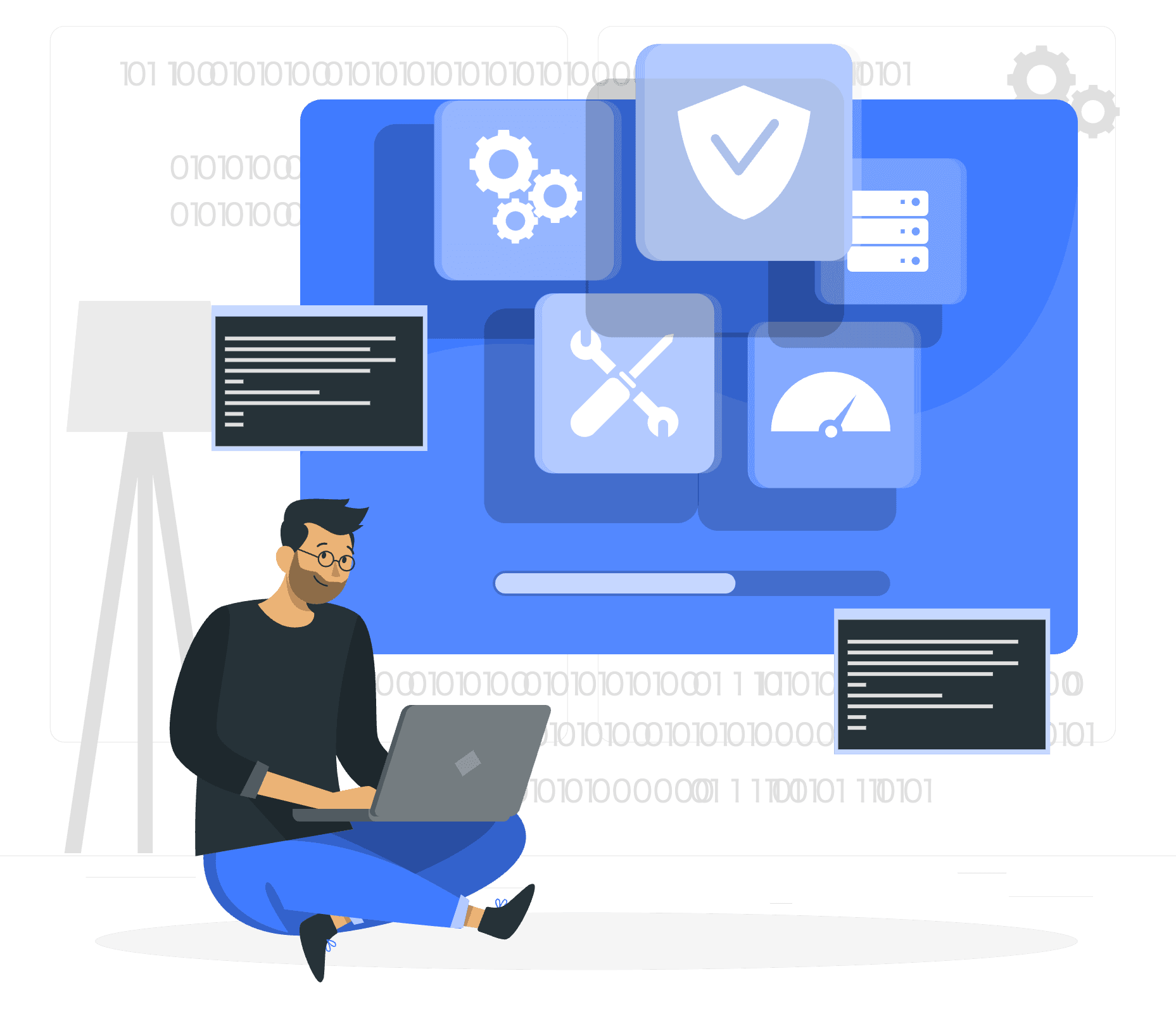
システムリプレイスを成功させるためには、計画的かつ段階的にプロセスを進めることが重要です。このセクションでは、プロジェクトチームの発足から、現行システムの課題分析、リプレイス計画の策定、開発パートナーの選定、そして段階的な移行とテストの実施まで、システムリプレイスを進める上での具体的なステップを解説します。リスクを最小限に抑え、効果的にシステムを刷新するためのポイントを理解しましょう。
プロジェクトチームの作成
システムリプレイスを成功させるためには、プロジェクトチームの適切な編成が最初の重要なステップです。経営層、IT部門、現場の担当者、そしてシステム導入を担当する外部パートナーなど、すべての関係者が参加するプロジェクトチームを作成します。
チーム内での役割分担を明確にし、進捗状況の管理やリスクの早期発見・対応ができるように体制を整えます。また、各ステークホルダーの意見を反映させるため、定期的なミーティングを実施し、プロジェクトの透明性を保つことが重要です。チームがしっかりと機能することで、リプレイスプロジェクト全体が円滑に進行します。
現行システムの課題を把握する
システムリプレイスのプロジェクトを進めるためには、まず現行システムの課題や問題点を明確にする必要があります。システムが古くなり、セキュリティリスクが増している、処理速度が遅い、メンテナンス費用がかさむなど、現行システムが抱える具体的な問題点を洗い出しましょう。
また、現場のユーザーからのフィードバックを収集し、業務に支障をきたしている箇所や、改善が必要なプロセスを特定します。この段階での課題の明確化が、リプレイスの目的やゴールを設定する際の基盤となり、成功に向けた方向性を定めるための重要なプロセスとなります。
目的とゴールを設定する
システムリプレイスの成功には、明確な目的とゴールを設定することが不可欠です。リプレイスの目的が、業務効率の向上、コスト削減、セキュリティ強化、または最新技術の導入による競争力強化など、どのような成果を目指すかを明確にします。
また、プロジェクト全体の最終的なゴールや成果指標(KPI)も設定し、プロジェクトの進捗を測定できるようにします。目的とゴールが明確であれば、プロジェクトチーム全体の方向性が統一され、リプレイスに伴うリスクや課題に対しても適切に対応できるようになります。
要件定義とリプレイス計画を策定する
要件定義は、システムリプレイスにおいて重要なステップであり、システムに求められる具体的な機能や性能を明確にするプロセスです。新しいシステムにどのような機能が必要か、どの業務プロセスにどのように対応するのかを詳細に定義します。次に、この要件に基づいてリプレイスの計画を策定します。
計画には、スケジュールや予算、リソースの配分、各段階でのチェックポイントなどを含め、全体のプロジェクトの進行がスムーズに行われるようにします。明確な要件定義と計画により、プロジェクトの成功率が格段に高まります。
適切な開発パートナーを選定する
システムリプレイスは高度な技術が求められるため、適切な開発パートナーの選定が重要です。開発パートナーは、システム開発や移行に関する専門知識を持ち、プロジェクトの目的や要件に対応できる技術力を備えていることが必要です。
定の際には、過去の実績、対応可能な技術分野、提供するサポート体制、そしてコストパフォーマンスを考慮して検討します。適切なパートナーを選定することで、プロジェクトのリスクが減り、リプレイス作業がスムーズに進行しやすくなります。また、パートナーとのコミュニケーションも円滑に行うことが重要です。
開発パートナーの選び方については次の記事にて詳しく解説していますので、併せてご確認ください!
段階的な移行とテストの実施
システムリプレイスは、一度に全てを移行するのではなく、段階的に行うことでリスクを最小限に抑えます。まずは一部の機能や部門で新システムを導入し、問題がないか確認しながら順次移行を進める「段階移行方式」がおすすめです。
この方法により、業務への影響を最小限にし、万が一問題が発生した際にも速やかに対応できます。移行ごとにテストを徹底的に実施し、システムが正確に機能していることを確認することで、トラブルを未然に防ぎます。また、システムの安定稼働が確認されるまで、旧システムとの並行稼働を行うことも効果的です。
システムリプレイスにおける4つの方法
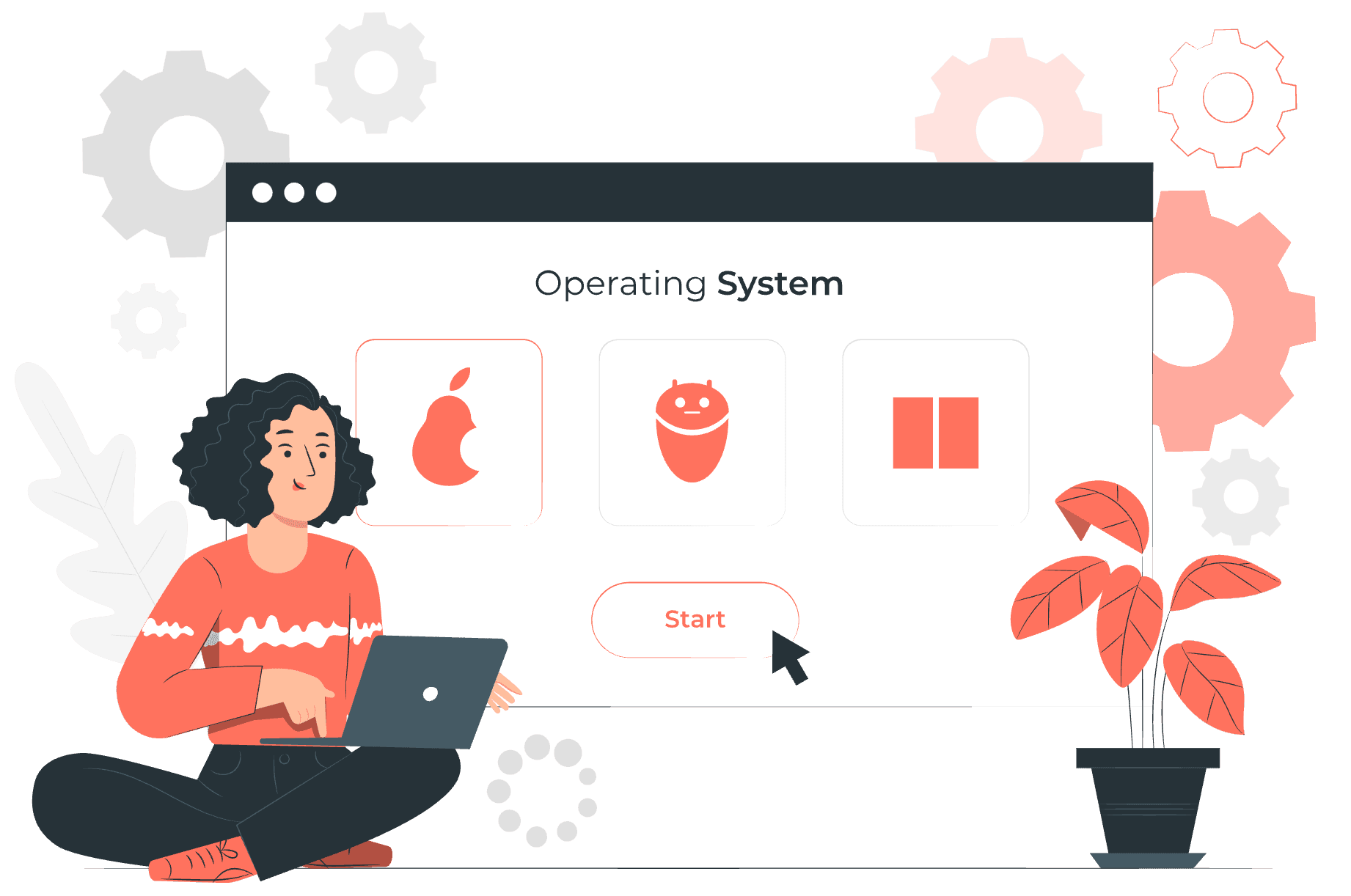
システムリプレイスを進める際には、状況に応じた適切な移行方式を選ぶことが重要です。本セクションでは、代表的な4つの移行方法である「一括移行方式」「段階移行方式」「並行移行方式」「パイロット移行方式」について解説します。それぞれの方法には特徴やメリット・デメリットがあるため、システムや業務の状況に合った選択が成功の鍵となります。
一括移行方式
一括移行方式は、旧システムから新システムに全てのデータや機能を一度に移行する方法です。すべての業務を一斉に新システムに切り替えるため、移行時間が短く、迅速な導入が可能です。ただし、トラブルが発生した場合には全業務に影響を及ぼすリスクが高いため、事前の準備とテストが非常に重要です。
特に、業務の中断が許されない企業にとっては、細心の注意が必要となります。この方式は、ダウンタイムを最小限に抑えたいプロジェクトや、システムが比較的小規模である場合に適しています。
段階移行方式
段階移行方式は、システムを部分的に移行しながら、旧システムとの併用期間を設ける方法です。新システムの一部機能を徐々に導入し、問題がないことを確認しながら次の段階に進めるため、リスクを最小限に抑えつつ移行を進めることができます。
移行期間が長くなるため、全体の移行作業に時間はかかるものの、トラブルが発生した際にも業務の影響を軽減することが可能です。この方式は、大規模なシステムリプレイスや、リスクを分散しながら確実に移行したい場合に適しています。
並行移行方式
並行移行方式は、旧システムと新システムを一定期間並行して稼働させる方法です。これにより、新システムの安定性を確認しながら移行を進められるため、リスクが低い点がメリットです。
また、並行運用により、従業員が新しいシステムに慣れるまで旧システムを利用できるため、トラブルが発生した際にも迅速に旧システムに戻ることが可能です。ただし、並行運用のためのコストや手間が増える点がデメリットです。業務を中断せず、安全に移行を進めたい場合に適した方法です。
パイロット移行方式
パイロット移行方式は、最初に一部の部署や限られた業務で新システムを導入し、テスト運用を行う方法です。これにより、新システムの安定性や適合性を確認し、問題点を修正した上で全体へ導入するかどうかを判断します。リスクを大幅に減らせるため、安全性が高く、特に大規模なリプレイスに適しています。
ただし、パイロット運用後に全社展開するためには時間がかかる場合があり、初期導入の効果が遅れる可能性があります。リスクを最小限に抑えつつ段階的に進めたい場合に効果的な方法です。
システムリプレイスを成功させる方法
システムリプレイスを成功させるためには、計画的な進行とプロジェクト全体の管理が不可欠です。このセクションでは、プロジェクトチームの適切な編成や、ステークホルダー間の連携、リスク管理、段階的な移行やテスト、ユーザー研修など、システムリプレイスを円滑に進め、成功に導くための重要なポイントについて詳しく解説します。
プロジェクトチームの適切な編成
システムリプレイスを成功させるためには、プロジェクトチームの適切な編成が不可欠です。経営層、IT部門、現場担当者、外部パートナーなど、各分野の専門家を含むチームを構成し、各メンバーの役割を明確にすることが重要です。
また、プロジェクトの進行を円滑に進めるため、チームリーダーを選定し、定期的なミーティングを行って情報共有を徹底します。各メンバーのスキルを活かし、チーム全体が一丸となって進行することで、リプレイスの各段階で適切な対応が取れるようになります。チームの連携がプロジェクトの成功の鍵を握ります。
ステークホルダー間の連携と合意形成
システムリプレイスは多くの関係者が関わるプロジェクトであるため、ステークホルダー間の連携が不可欠です。経営層、IT部門、現場の担当者など、各ステークホルダーの意見やニーズを取り入れながら、プロジェクトの目的やゴールについての合意を形成することが重要です。
各ステークホルダーが共通の目標を持ち、プロジェクトの進行に対して同じ方向を向いていることで、スムーズな意思決定が可能となります。定期的なコミュニケーションを通じて、意見のすり合わせを行い、トラブルや不一致を事前に防ぐことがリプレイス成功の要因となります。
リスク管理とトラブル対応の計画
システムリプレイスには、さまざまなリスクが伴います。データ移行の失敗や業務停止、システムの不具合など、予期しないトラブルが発生する可能性を考慮し、リスク管理計画を策定することが重要です。
リスクを最小限に抑えるために、事前に考えられる問題を洗い出し、それに対する対応策や緊急時の対応フローを準備します。さらに、プロジェクトの各段階でリスクを監視し、問題が発生した場合には迅速に対応できる体制を整えることで、トラブルを未然に防ぎ、リプレイスを円滑に進めることができます。
段階的な移行と徹底的なテストの実施
システムリプレイスでは、一度に全てのシステムを移行するのではなく、段階的に移行を進めることがリスクを最小限に抑える鍵です。まずは一部の機能や部門で新システムを導入し、その後問題がないことを確認しながら次のフェーズに進めるのが一般的です。
また、移行の各ステージで徹底的なテストを実施し、システムが正確に動作しているか確認することも重要です。テストを省略せずに行うことで、リプレイス後のトラブルを防ぎ、システムが円滑に稼働することを確保します。
ユーザー研修とサポート体制の構築
新システムに移行した後、従業員がスムーズに新しいシステムを使いこなせるように、適切な研修を行うことが必要です。ユーザーが新システムの操作に慣れないと、業務効率が低下するリスクがあるため、従業員のスキル向上をサポートする研修プログラムを提供します。
また、システム導入後もサポート体制を整え、トラブルが発生した際には迅速に対応できる窓口を設けることが重要です。適切なユーザーサポートによって、従業員が安心して新システムを活用できるようにすることが、システムリプレイスの成功に繋がります。
プロジェクト進捗の定期的な確認と調整
システムリプレイスのプロジェクトは、定期的な進捗確認と計画の見直しが重要です。プロジェクトがスケジュール通りに進行しているか、リソースの割り当てに問題がないかを定期的に確認し、必要に応じて調整を行います。
また、プロジェクトの進捗状況をチーム全体で共有することで、問題が発生した際には早期に対処できる体制を整えます。定期的な報告とフィードバックのプロセスを組み込むことで、リプレイスプロジェクト全体を正しい方向に導くことができます。

開発オクトパス
まとめ
システムリプレイスは、企業が最新技術を導入し、業務効率やセキュリティを強化するために重要なステップです。メリットが大きい反面、初期費用や業務停止のリスク、従業員トレーニングなど、考慮すべき課題も存在します。
成功のためには、プロジェクトチームの編成やリスク管理、段階的な移行とテストの実施が不可欠です。計画的に進めることで、企業の成長を支えるシステム移行が実現します。この記事が、システムリプレイスを検討する際の参考になれば幸いです。
Illustration by Storyset

この記事の著者
井上雄太
株式会社SALTOにWebエンジニアとして新卒入社。エンジニアとしてWebアプリ開発の業務を経験したのちにマーケティング職に転向。記事のライティングやSNS運用業務を担当。