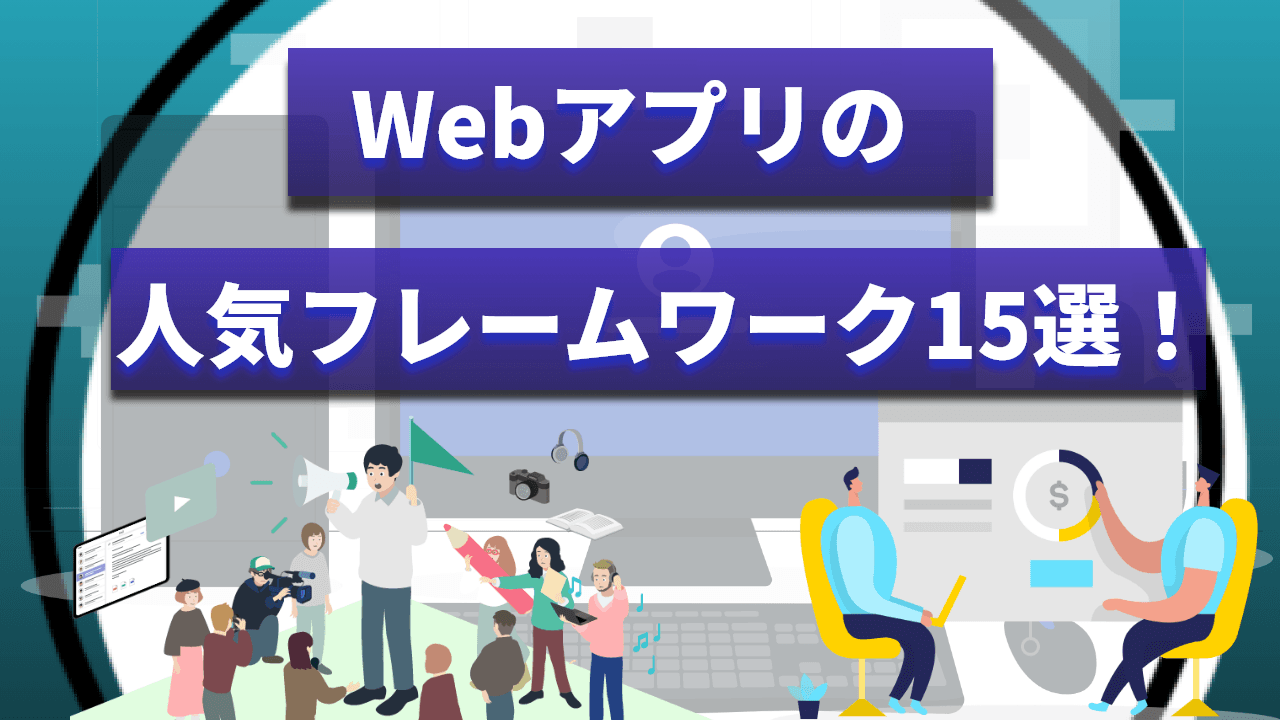WEBシステムとは何か?導入例を踏まえて仕組みを詳しく解説
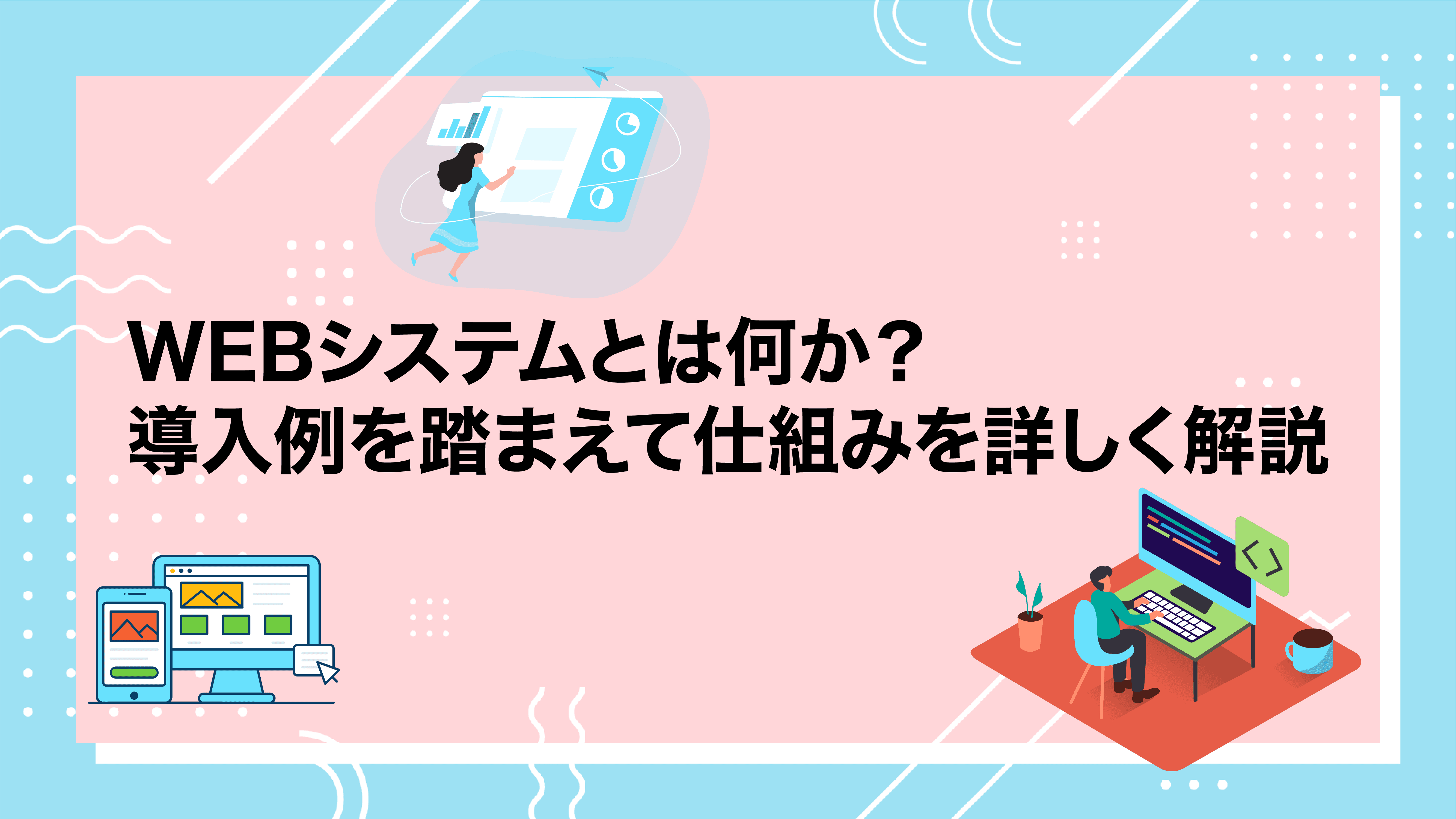
業務効率化やDX化が進む現在、WEBシステムはビジネスに不可欠な要素です。しかし、そもそもWEBシステムとは?と感じる方もいるかと思います。
この記事では、WEBシステムの基本概念から具体的な事例、導入のメリットや注意点までを丁寧に解説します。
さらに、WEBシステム開発における一般的な用語や流れにも焦点を当て、システム開発のプロセスを理解しやすくします。ビジネスにおけるWEBシステムの重要性や効果的なシステムの導入・活用に向けた知識を身につけられるようにします。
また、おすすめのWEBシステム開発会社を探している方は下記記事を参照ください。
WEBシステムとは?
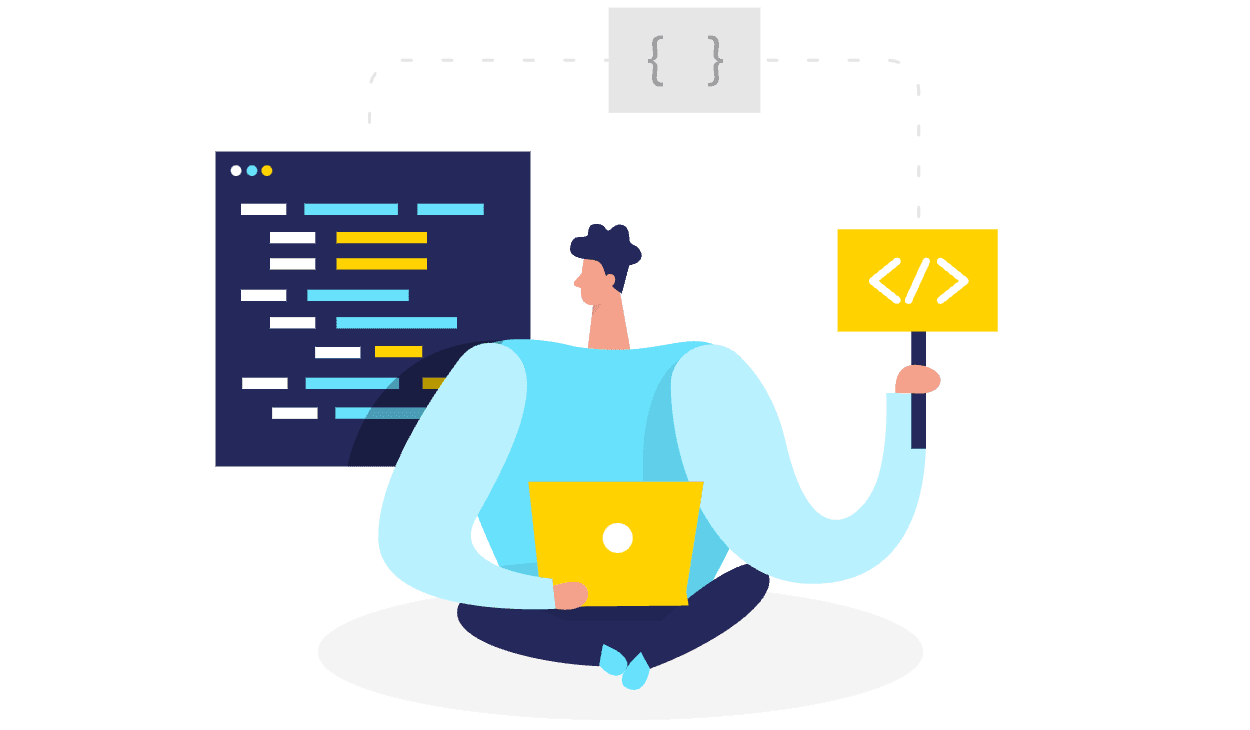
WEBシステム、WebアプリケーションやWebサイトなど似たようなワードを耳にする機会が多いかと思います。
一部同義語として扱われることがありますが、本セクションではその違いを開設していきます。また、クライアントサーバーシステムやスタンドアロンシステムとの比較、他の種類のシステムとの違いにも触れ、WEBシステムの位置づけを明確にします。
WEBシステムとWEBアプリケーションの違い
WEBシステムとWEBアプリケーションは同じ意味合いで使われることもありますが、狭義ではWEBアプリケーションは単一のアプリケーションを指し、WEBシステムは複数のアプリケーションやサービスを含むシステム全体を指します。
なので、WEBシステムとWEBアプリケーションは機能としては同じであるが規模が異なるということになります。
WEBシステムとWEBサイトの違い
WEBシステムとWEBサイトの最大の違いは、目的と機能です。WEBサイトは情報の提供やコンテンツの閲覧を主な目的としていますが、WEBシステムはデータの処理や操作、ユーザーとのインタラクションを可能にする機能を持ちます。WEBシステムは通常、データベースと連携し、ユーザーが入力した情報を処理して結果を返す能力を持っています。
WEBシステムとクライアントサーバーシステムの違い
WEBシステムとクライアントサーバーシステムの主な違いは、システムの構成にあります。WEBシステムは、クライアント側でのアプリケーション実行を必要とせず、Webブラウザを介して全ての処理を行います。
一方、クライアントサーバーシステムでは、クライアントがリクエストを送信し、サーバーがデータ処理や要求への応答を行います。
WEBシステムはWEBブラウザだけあれば利用できるのに対して、クライアントサーバーシステムは特定のソフトがなければ利用できない点が大きく異なる点になります。
WEBシステムとスタンドアロンシステムの違い
WEBシステムとスタンドアロンシステムの主な違いは、アクセス方法と環境です。
WEBシステムはWebブラウザを介してアクセスされ、インターネットや社内ネットワークを通じて利用されます。
一方、スタンドアロンシステムは特定の端末やローカルネットワーク内で動作し、ユーザーが特定の端末でアプリケーションを直接実行します。
WEBシステムはリモートからのアクセスが可能であり、スタンドアロンシステムは限られた環境でのみ利用可能です。
その他のシステム
その他のシステムとして、組み込みシステムが挙げられます。組み込みシステムは、特定の機器やデバイス内に組み込まれ、その機能を制御・管理するためのシステムです。
例えば、自動車のエンジン制御システムや家電製品の制御システム、産業機械の制御システムなどがあり、これらのシステムは、一般的なコンピューターとは異なり、専用のハードウェアやリアルタイム性を要求される場合があります。
組み込みシステムは、制御や監視などのタスクに特化しており、ユーザーが直接操作することは少ない傾向があります。

開発オクトパス
WEBシステムできること・導入事例
WEBシステムは多岐にわたる用途に活用され、様々な業種やビジネスに貢献しています。本セクションでは、WEBシステムが実現する機能や役割に焦点を当て、その導入事例を紹介します。SaaSやポータルサイト、ECサイト、予約システムなど、さまざまな事例を通じてWEBシステムを解説します。
Saas
SaaS(Software as a Service)は、クラウド上で提供されるソフトウェアサービスのことを指します。ユーザーはインターネット経由でアクセスし、サービスを利用するため、自社のインフラストラクチャーを必要としません。
企業はSaaSを活用して、オフィスアプリケーションやCRM、プロジェクト管理ツールなどのソフトウェアを柔軟に導入し、月額または利用量に応じて料金を支払います。SaaSは導入コストを低減し、柔軟性とスケーラビリティを提供するため、多くの企業にとって魅力的な選択肢となっています。
SlackやZoom、マネーフォワード クラウドなどがSaasの代表例となります。
ポータルサイト
ポータルサイトは、インターネット上の情報を集約し、ユーザーにとって便利な情報やサービスを提供するWEBサイトです。あらゆる情報を一つのポータルからアクセスできるようにします。
ユーザーはポータルサイトを通じて複数の情報やサービスにアクセスし、個々のウェブサイトに移動する手間を省くことができます。ポータルサイトはユーザーにとって情報の入口となり、便利で使いやすい環境を提供します。
ECサイト
ECサイトは、Electronic Commerce Site(電子商取引サイト)の略称で、インターネット上で商品やサービスを販売するためのウェブサイトです。
顧客は商品を閲覧し、選択した商品をカートに入れて購入手続きを行います。ECサイトでは、セキュリティ対策や決済システムの導入など、オンライン上での安全な取引を実現するための機能が重要です。
また、顧客の利便性を向上させるための機能として、商品検索やレビュー、注文履歴の管理なども提供されます。
SNS
SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)は、ユーザーが自分のプロフィールを作成し、友人やフォロワーとのつながりを構築し、コンテンツを共有するウェブサイトです。
WEBシステムとして、ユーザーはブラウザを介してSNSにアクセスし、投稿やコメント、メッセージのやり取りを行います。
SNSは個人同士のコミュニケーションを促進するだけでなく、企業やブランドが顧客との関係を構築し、マーケティング活動を展開するプラットフォームとしても活用されています。
予約システム
予約システムは、顧客がオンラインでサービスや施設の予約を行うためのシステムです。
WEBシステムとして、ユーザーはブラウザを介してSNSにアクセスし、投稿やコメント、メッセージのやり取りを行います。
WEBシステムとして、顧客は予約フォームに情報を入力し、事業者は予約状況を管理します。予約確定後、顧客には予約の確認やリマインダーが送信され、便利でスムーズな予約手続きが可能です。

開発オクトパス
WEBシステムを活用するメリット
WEBシステムを活用することには多くのメリットがあります。このセクションでは、5つの視点からメリットについて解説します。
業務効率改善
WEBシステムを導入することで、業務効率を大幅に改善できます。
業務プロセスの自動化やデータの集約化により、作業時間が短縮され、作業の精度や品質が向上します。
また、リアルタイムでの情報共有やコラボレーションが可能になるため、チーム全体での効率化が図れます。さらに、タスクの追跡や管理が容易になり、業務全体の可視化が促進されます。
メンテナンスが行いやすい
WEBシステムは、それぞれのユーザーの端末にデータが存在するわけではなく、サーバー上にプログラムやデータが存在しているため中央集権的な管理が可能です。
なのでシステムのアップデートや修正を一括して行うことができメンテナンスが行いやすいです。
汎用性が高い
WEBベースのシステムは、特定の業務に限定されず、さまざまな目的に応用できます。
また、場所やデバイスに依存せずにアクセスできるため、柔軟性が高く、利用範囲が広がります。これにより、企業は様々なニーズに対応し、ビジネスの成長や変化に柔軟に対応できます。
運用コストが低い
WEBシステムの運用コストが低いのは、複数の理由があります。
クラウドベースの運用では、自社のサーバーの設置やメンテナンス、セキュリティ対策などの費用が不要になります。
また、従量課金やサブスクリプションモデルにより、必要なサービスや機能だけを支払うことができ、無駄な費用を抑えることができます。
どこからでもアクセス可能
WEBシステムは、どこからでもアクセス可能なため、利用者はオフィスや自宅、外出先など、場所に制約されずにシステムにアクセスできます。
インターネット環境さえあればそれぞれのデバイスからアクセス可能になるので円滑に業務を進めることが可能です。

開発オクトパス
WEBシステムを活用するデメリット
先ほど挙げたようにWEBシステムを活用することにはたくさんのメリットが存在します。しかし、一方でデメリットも存在するのでこのセクションではそのデメリットについて解説していきます。
セキュリティを意識する必要がある
WEBシステムを活用する際のデメリットの一つは、セキュリティへの懸念です。
オンライン上でのデータのやり取りやアクセスは、悪意のある第三者による不正アクセスや情報漏洩のリスクを孕んでいます。
そのため、適切なセキュリティ対策が必要であり、定期的なセキュリティの評価やアップデートが不可欠です。また、従業員の教育や意識向上も重要であり、セキュリティに関する十分な対策を講じる必要があります。
導入コストが高い
WEBシステムの導入コストは、企業やプロジェクトの規模や要件によって異なりますが、数百万円から数千万円に及ぶことが一般的です。
例えば、カスタム開発やシステムの構築には開発者やエンジニアの人件費がかかりますし、専用のサーバーの導入やインフラ整備にも大きな費用が必要です。
障害発生時の影響範囲が広い
WEBシステムでは、障害発生時の影響範囲が広くなるデメリットがあります。
システムがオンライン上にあるため、障害やサーバーダウンが発生すると、全てのユーザーに影響を及ぼす可能性があります。
通信環境が必要不可欠
先ほどメリットとして、インターネット環境さえあればアクセス可能と解説しましたが、逆に言えばインターネット環境がなければアクセスできません。
これもデメリットの1つとも考えられます。
WEBシステム開発の流れ
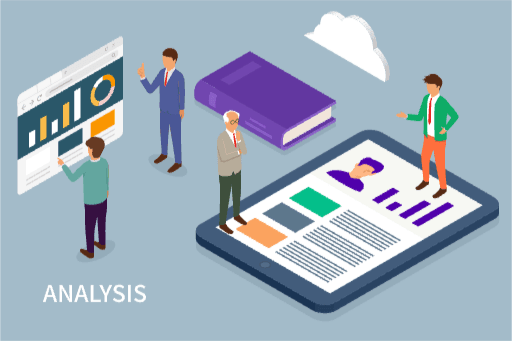
WEBシステム開発の流れを理解することは、プロジェクトの成功に欠かせません。このセクションでは、システム開発の各段階について詳しく解説し、効果的なプロジェクト管理の手法を紹介します。
システム開発の目的/要件の整理
システム開発の目的/要件の整理は、プロジェクトの成功に不可欠です。
システム開発会社にシステムの開発を発注する前に、システムを開発することになった経緯、ニーズや目的を明確に整理してシステムが達成すべき機能や要件を洗い出します。
目的や必要な機能を整理することでシステム開発会社との連携がスムーズに行えるようになります。
見積もり依頼
見積もり依頼は、プロジェクトの予算やスケジュールを決定する上で重要です。
複数社に見積もりを依頼することで、価格や提供されるサービスの比較が可能になります。また、異なる企業からの提案を受けることで、新たなアイデアやアプローチを得ることもできます。
これにより、より適切な開発パートナーを選択し、プロジェクトの成功につなげることができます。
発注
複数社に見積もりを依頼し、どのパートナーに依頼するか決定したらいよいよ発注です。
発注は、選定した開発パートナーとの契約を行う重要な段階です。プロジェクトの範囲や納期、費用などの条件を明確にし、正式な開発作業の開始を確定させます。
要件定義
要件定義は、システムが満たすべき機能や要件を具体化する作業です。
システム開発会社とのコミュニケーションを通じて、システムの必要性や目標を明確にし、具体的な要件を抽出します。要件定義はプロジェクトの基盤であり、開発チームがシステムを正しく理解し、システムがニーズ/期待に応えられるための基準を確立します。
設計
設計段階では、要件定義を元にシステムのアーキテクチャやデータベース構造などを設計します。
この段階では、システムの全体像を描き出し、各機能やモジュールの関係性を明確にします。適切な設計により、効率的で拡張可能なシステムを構築するための基盤を築きます。
また、設計段階での検討やレビューによって、後の開発作業の円滑な進行を確保します。
実装
実装段階では、設計されたシステムをコード化し、具体的な機能や機能を開発します。
プログラミング言語やフレームワークを使用して、要件に基づいたソフトウェアを作成し、テスト可能な状態にします。
開発者は、要件定義と設計段階で定められた仕様に従って、コーディングを行い、システムの機能を実現します。
テスト
テスト段階では、開発されたシステムが要件を満たし、正しく動作することを確認します。
様々なテストケースを用いて、システムの機能や性能、セキュリティなどを検証し、バグやエラーを発見して修正します。
テストは、ユーザーが期待通りにシステムを利用できるかどうかを確認する重要な工程であり、品質の確保と安定した運用を支えます。
リリース(納品)
リリース(納品)は、開発されたシステムをユーザーに提供する段階です。テストを経て品質が確保されたシステムが、顧客の要求や期待に応えるかどうかを確認します。
リリース前には、十分なユーザーテストやトレーニングが行われ、ユーザーがシステムを効果的に活用できるようサポートされます。
運用
運用は、システムがユーザーのニーズを満たし続けるための継続的な管理とサポート活動です。
システムの安定性やパフォーマンスを維持し、新たな要件や変更に対応し、ユーザーサポートやトラブルシューティングを行います。
運用は、システムの効果的な利用を促進し、ビジネス目標の達成を支援します。

開発オクトパス
WEBシステム開発で用いられる単語
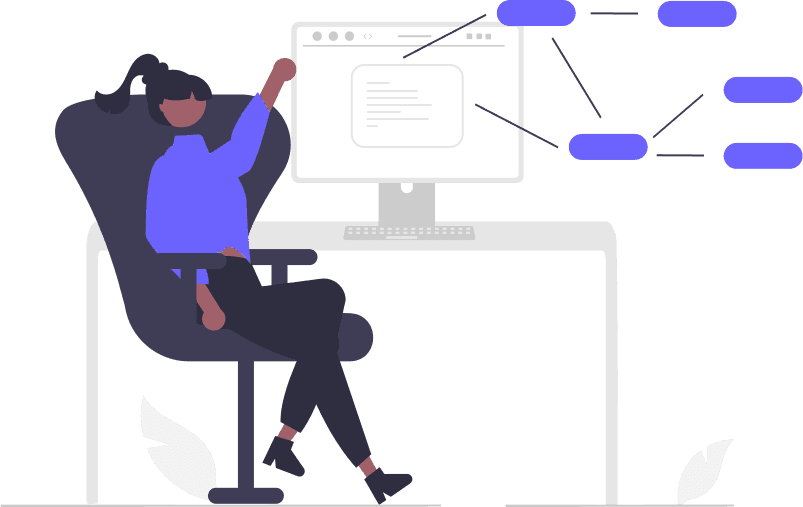
このセクションではWEBシステムを扱う際に頻出する単語について解説していきます。
サーバーサイド
サーバーサイドは、WEBシステムのバックエンド側で実行される処理を指します。
クライアント(ユーザー側)からのリクエストを受け取り、データの処理やビジネスロジックを実行し、結果をクライアントに返す役割を担います。
クライアントサイド
クライアントサイドは、ウェブページやWEBシステムのユーザー側で実行される処理を指します。
ブラウザ上で動作し、ユーザーの操作に応じてインタラクティブな動作や表示を提供します。
HTML、CSS、JavaScriptなどの技術がクライアントサイドで利用され、ユーザーのデバイス上で実行されます。
プログラミング言語
クライアントサイドの説明でも出てきたように、WEBシステムを扱う際にはプログラミング言語がよく登場します。
ここでは代表的なプログラミング言語をいくつか紹介します。
・HTML
HTML(HyperText Markup Language)は、ウェブページの構造を定義するためのマークアップ言語です。
クライアントサイドでブラウザによって解釈され、ページの構造やコンテンツの表現を可能にします。
主にクライアントサイドで使用され、Webページの構造、テキスト、画像、リンクなどを記述し、ブラウザに表示される内容を定義します。
・CSS
CSS(Cascading Style Sheets)は、ウェブページのスタイルやレイアウトを定義するためのスタイルシート言語です。
クライアントサイドでブラウザによって解釈され、HTMLで記述されたコンテンツの見た目や装飾を管理します。
文字の色やサイズ、背景色や画像、レイアウトの配置などを指定し、ウェブページのデザインを一貫性のあるものに整えます。CSSはHTMLと組み合わせて使用され、見栄えやユーザーエクスペリエンスを向上させます。
・JavaScript
JavaScriptは、ウェブページやウェブアプリケーションの動的な動作やインタラクティブな機能を実装するためのプログラミング言語です。
クライアントサイドでブラウザによって解釈され、ユーザーの操作に応じてページの動作を変更したり、動的なコンテンツを生成したりすることができます。
たとえば、フォームの入力検証、アニメーションの実装、APIからのデータ取得などが可能です。JavaScriptはHTMLやCSSと組み合わせて使用され、ウェブページの機能性とユーザーエクスペリエンスを向上させます。
・PHP
PHPは、サーバーサイドで動作するプログラミング言語です。
PHPは、データベースとの連携やファイルの操作、セッション管理などのサーバーサイド処理を行います。
動的なウェブページの生成や、フォームのデータの処理、ログインシステムの実装など、さまざまなWEBシステムの開発に利用されます。
・Java
Javaは、オブジェクト指向のプログラミング言語で、サーバーサイドで動作する言語です。
プラットフォームに依存しない特性と豊富なライブラリがあり、高い信頼性と開発効率を提供します。
フレームワーク
フレームワークは、WEBシステム開発における基盤となる構造やルールを提供するソフトウェアの集合体です。
特定の目的に合わせて設計され、一般的な機能やタスクを自動化し、開発者がシステムの構築に集中できるようサポートします。
フレームワークには、WEB開発、モバイルアプリ開発、テスト自動化など、さまざまな種類があります。
ウォーターフォール型
ウォーターフォール型は、システム開発のプロセスを段階的に進める伝統的な手法です。
要件定義、設計、実装、テスト、リリースといった一連の工程を順次進め、各段階が完了すると次の段階に進む形式です。
各段階での変更は困難であり、開発の初期段階での要求変更が後の段階に大きな影響を与えることがあります。
アジャイル型
アジャイル型は、柔軟性と迅速な反応性を重視するシステム開発手法です。
従来のウォーターフォール型のような段階的な進行ではなく、短い開発サイクル(スプリント)を繰り返し、顧客のフィードバックや要求変更に対応します。
開発チームは自己組織化され、継続的な改善を重視します。アジャイル型はリスクの低減や顧客満足度の向上を目指し、効率的で柔軟な開発プロセスを実現します。
まとめ
今回の記事では、WEBシステムに関して導入のメリットやデメリット、実際に開発する際の流れなどを解説しました。
WEBシステムの開発をお考えの方は何かしらシステムを用いて解決したい課題があるかと思います。まずはその課題を明確にしてどのようなシステムが必要なのかをしっかり理解し、システム開発会社と連携していくことで課題解決が近づくと思います。
今回の記事が少しでも参考になれば幸いです。

この記事の著者
井上雄太
株式会社SALTOにWebエンジニアとして新卒入社。エンジニアとしてWebアプリ開発の業務を経験したのちにマーケティング職に転向。記事のライティングやSNS運用業務を担当。